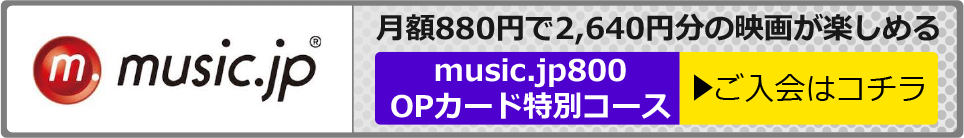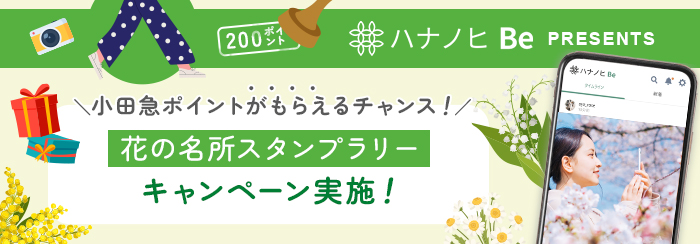特集・コラム
映画のとびら
2022年5月13日
犬王|映画のとびら #180

 ©2021 “INU-OH” Film Partners
©2021 “INU-OH” Film Partners実在の能楽師・犬王(いぬおう)を描く古川日出男の人気小説『平家物語 犬王の巻』(2017年刊)を映像化した長篇アニメーション。才能にあふれながら権力に翻弄される能楽師と琵琶師、ふたりの男の奇想天外な半生をダイナミックに描く。脚本にテレビドラマ『「逃げるは恥だが役に立つ』(2016)の野木亜紀子。キャラクター原案に『ピンポン』(2002)、『鉄コン筋クリート』(2006)の原作者・松本大洋。監督は『マインド・ゲーム』(2004)、『夜は短し歩けよ乙女』(2017)の湯浅政明。
室町時代にふたりの少年がいた。ひとりは、壇ノ浦で父親とともに平家の遺物を漁っていた友魚(ともな/声:森山未來)。三種の神器のひとつである「剣」の呪いで視力を失った彼は、やがて老琵琶法師に弟子入り、琵琶の奏法を得て、都をさすらう身となる。
もうひとりは、猿楽能の一派「比叡座」の跡継ぎとして生まれながら、異形の姿ゆえに犬のような人生を歩んできた少年(後の犬王/声:アヴちゃん[女王蜂])。見よう見まねで能の舞を会得し、才気を覚醒させていった彼は、都大路で友魚と出会う。セッションで意気投合したふたりは、それぞれ友有(ともあり)、犬王と名乗り、京の端々で圧巻のパフォーマンスを繰り返していくのだった。
伝記ドラマというより、伝奇ロマン。琵琶師の友魚はもとより、史料がほとんど残されていない犬王にしても想像が羽ばたく限りの肉付けが施されている。歴史の波間に消えていった伝説の能楽師とはいったいどのような人物だったのか。どんな存在感を大衆に示していたのか。ミステリーと幻想譚の味わいが絶妙に絡み合って、能楽にうとい人間でもいとも簡単に時間の彼方へ連れて行かれる。
この世の者とは思われぬ姿の犬王がたどる有り様には、監督の湯浅政明が述懐しているとおり、手塚治虫の名著『どろろ』(1967-1969)における百鬼丸を連想させるだろう。しかし、手塚漫画と異なり、天才能楽師の人生は安易に明るい方向へ向かわない。歴史の常として「個」は容赦なく「現実」に踏み潰されようとする。あらがえぬ時代への抵抗は当然、ロマンティックであり、美しい。現代日本の風景から始まる物語は、600年前のそれを「今」と地続きの青春ドラマとしてもよみがえらせようとした。実際、「政治」に揉まれる青年たちのあがきは普遍的なものだろう。やんちゃであればあるほど、愛おしい。
「今」感ということでは、犬王と友魚が見せて聞かせる音楽と踊りの表現が大きい。どこか物語を二の次にするほど、パフォーマンス描写は念入り。友魚がつま弾く琵琶はギター同然であり、犬王の舞などコンテンポラリーダンスさながらにアクロバティック。奏でられる音楽もパンクロック的な気分を醸しており、もはや琵琶師も能楽師もロックスター。映画自体がひとつのライヴになっている。我々はそのステージを目撃する聴衆だ。いざとなれば、細かい歴史の講釈など頭から飛ばして、興奮にただ身を任せておけばいい。
湯浅政明の映像表現は例によって奇抜にして緻密。引き画(え)の芝居の美しさ、りりしさはやはり格別で、人間の生活感、かの時代の生活感も無理なくにじむ。友魚の盲目世界を生かした映像、犬王の身体をめぐる作画にも工夫が凝らされており、とりわけ安徳天皇の自死をめぐる描写のあっけなくも衝撃的な手際といったらない。イマジネーションの果てを行く、めくるめくような絵の動きを眺めているだけで、98分という尺はあっという間。音楽とのリンクでいけば『夜明け告げるルーのうた』(2017)、『きみと、波にのれたら』(2019)の情景も見つけられるだろう。なんと絢爛豪華、大胆不敵な仕掛けの数々。現代アニメーション界最高の映像創作者もまた時代を超える琵琶法師にして能楽師なのであった。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。