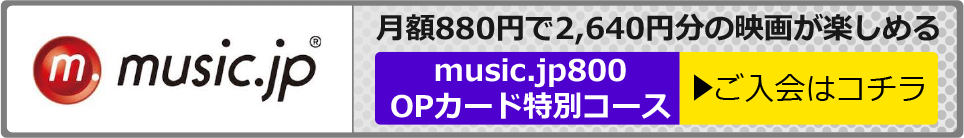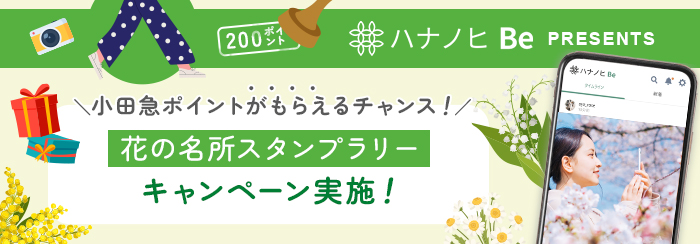特集・コラム
映画のとびら
2022年6月17日
リコリス・ピザ|映画のとびら #187【特製プレスシートプレゼント】

 © 2021 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED.
© 2021 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED.『マグノリア』(1999)、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2005)のくせ者監督ポール・トーマス・アンダーソンによる青春コメディー。1970年代のハリウッドを舞台に、男子高校生とカメラマンアシスタントの女性、10歳差カップルの恋の行方が描かれる。男子高校生ゲイリーに、アンダーソン作品の常連俳優だった故フィリップ・シーモア・ホフマンを父に持つクーパー・ホフマン。カメラマンアシスタントのアラナに、姉妹バンド「HAIM」のメンバーであるアラナ・ハイム。いずれも、これが映画初出演。第94回アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚本賞の候補となった。
物語は1973年、サンフェルナンド・バレーにある高校で行われた写真撮影会で始まる。ゲイリーは子役として俳優活動をしている少年。ひと目見るなり、アラナに心を引かれた彼は、やがてデートに誘い出すことに成功。一方、当初はマセたガキにしか見ていなかったアンナだったが、やがてゲイリーに妙な商才があることを知り、彼がウォーターベッドの販売を始めると、ビジネスパートナーとして一緒に働き始める。つかず離れずの関係性のまま時を重ねていく彼らの姿がおかしくも微笑ましい。
題名の『Licorice Pizza』とは、かつてアメリカで若者たちに人気を集めたレコード店の名前とのこと。グミのような食感の「リコリス菓子」を連想させる部分も含めて、かの時代への郷愁が全編を甘く覆っている。往事を知らない若い観客には、逆にポップで新鮮な70年代体験となるだろうか。劇中には60-70年代のポップナンバーが所せましと流れて、耳からも楽しいカリフォルニアの風景なのであった。
90年代後半に彗星のように登場したアンダーソンだが、ここ15年ほどはダニエル・デイ=ルイス、フィリップ・シーモア・ホフマン、ホアキン・フェニックスらを擁しての、独特にして彫りの深い「歴史探訪」が監督作品の多数を占めた。それはそれでひとつの「美学」であったが、様式的な角度からの視点が懐古趣味と重なって、鈍重となる瞬間もあったのではないか。それに比べると、この70年代恋愛喜劇は終始、モタモタとしながらもドラマの風通しがよく、登場人物たちも軽妙に弾む。最近のアンダーソン作品にないワクワクをもたらす。なぜか。理由のひとつに、主演俳優陣の存在を挙げてもいいだろう。
クーパー・ホフマンとアラナ・ハイムはお世辞にも美男美女とは言いがたい。むしろ、どこにでもいそうな平均的な庶民感が出ていたりする。しかも、これがほとんど最初の演技経験。経験も技術もない。あるのは、そこに立ったときの素の感触のみ。恐らく、ポール・トーマス・アンダーソンはこのふたりを主人公カップルに据えることで、近年、自身からにじんでいた「作家的臭み」を自ら封じたのではないか。あるいは、彼らを中心に置くことで、作家的閉塞感からの打破をもくろんだのではないか。
それほどに、この主演男女、得も言われぬ「素人の個性」があふれていた。ヘアスタイルやファッションを除いても、彼らの表情には手練手管の及ばない古き良き時代がにじみ、いわば「原始の人間的温もり」。個性がなさげで、でも実は抑えようもなくあふれるそれは、アンダーソンにも手にあまるほどであったろう。そんな彼らを最大限に生かし、自由にさせようとしたとき、演出のよこしまな欲は消えた。恐らく、どこまでも素直になった。寛容になった。いつまでも、このふたりの姿を眺めていたい。どうにかして恋を実らせてあげたい。そんな観客の声は、実のところ、アンダーソンの声でもあったのではないか。
仕掛けがないわけではない。ショーン・ペンは無軌道な映画スターを戯画的に演じ、トム・ウェイツはペンの行動にさらなる油を注いで大暴れ。ブラッドリー・クーパーはといえば、これまた破天荒の一語に尽きる伝説的映画プロデューサー、ジョン・ピータースに挑み、笑いの爆弾と化した。とはいえ、彼らが前面に出続けることはない。アンダーソンにとって、ギリギリの「お遊び」だったのだろう。
強いてアンダーソン作品に類似を求めるなら、『パンチドランク・ラブ』(2002)あたりが該当するだろうか。同作もまた、ひと目惚れの恋愛を可愛らしくつづった小品だった。
人気監督の座に上りつめて以来、最も地味な面々を主役に置きながら、アンダーソンは最近まで見失っていた素朴な心の優しさ、美しさをこの小さな恋愛劇で取り戻すことができた。リフレッシュできた。監督、観客、双方にとって、宝石のような瞬間が、この作品には確実にある。
公式サイトはこちら
「リコリス・ピザ」の特製プレスシートをプレゼント
「リコリス・ピザ」の特製プレスシート(非売品)を
抽選で3名さまにプレゼント!
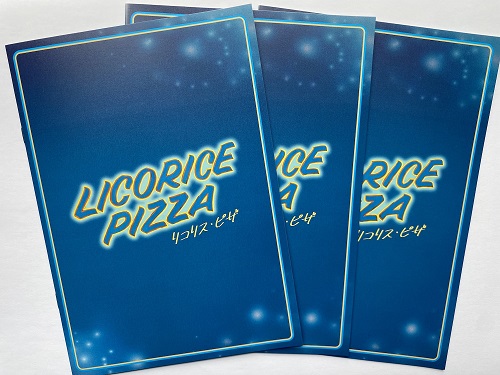
◆ご応募はOPカードWEBサービスからエントリーしてください。
<応募期間:
2022年6月17日(金)~7月10日(日)>
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
ポール・トーマス・アンダーソンはギャンブルの世界を見つめた『ハード・エイト』(1996)で商業長篇デビューを飾っている。続く『ブギーナイツ』(1997)では、1970年代のポルノ業界を骨太かつ辛辣に切り取るなど、題材と視点の新鮮さが映画ファンの心をわしづかみにした。第70回アカデミー賞では脚本賞、助演男優賞(バート・レイノルズ)、助演女優賞(ジュリアン・ムーア)の候補になった。
一般に注目されるきっかけとなったのは『マグノリア』(1999)だろう。トム・クルーズのワイルドかつエモーショナルな端役出演、カエルが空から舞い降る突飛なシーンなどもあり、ポップな映画監督との印象を世間に植え付けた。第72回アカデミー賞では脚本賞、助演男優賞(トム・クルーズ)、主題歌賞(エイミー・マン)の候補になっている。
アダム・サンドラーとエミリー・ワトソンの顔合わせで描くラブロマンス『パンチドランク・ラブ』(2002)では第55回カンヌ映画祭で監督賞を獲得。この作品まで、どこかポップな感覚で大衆人気を得てきたわけだが、次なる『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2005)では一転、アメリカの石油王を描くために重厚な人間ドラマへと大きく作風の舵を切った。第78回アカデミー賞で主演男優賞(ダニエル・デイ=ルイス)と撮影賞(ロバート・エルスウィット)を受賞した同作品に続き、『ザ・マスター』(2012)では新興宗教の世界に足を踏み入れ、『インヒアレント・ヴァイス』(2014)では1970年代のロサンゼルスを舞台に私立探偵の姿を軽妙とハードボイルドの狭間に追った。
再びダニエル・デイ=ルイスと顔を合わせた『ファントム・スレッド』(2017)は、1950年代のロンドンを舞台にオートクチュールの世界を描いたもの。デイ=ルイスは仕立屋の役。題材、表現は異なるが、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』の残り香は確かにここにあり、映像の様式美も大きく際立った。
『リコリス・ピザ』(2021)が『パンチドランク・ラブ』同様、「幕間の軽妙作」的位置にあるとしたら、アンダーソンは今後また新たな様式の世界へと深く沈んでいくというのだろうか。わからない。だが、それが刺激的な作品になることだけは疑いのないところだろう。奇才の動向からはまだまだ目が離せない。
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。