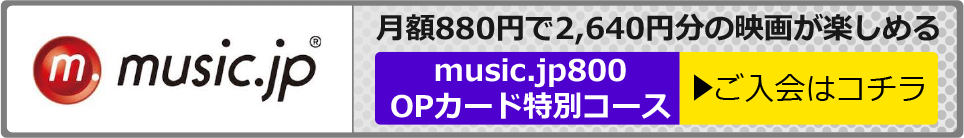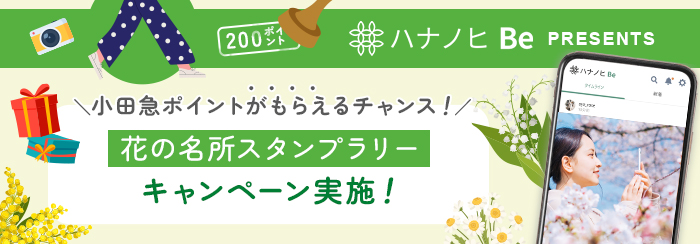特集・コラム
映画のとびら
2022年8月18日
セイント・フランシス|映画のとびら #198

 (C) 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED
(C) 2019 SAINT FRANCES LLC ALL RIGHTS RESERVED6歳の少女の子守をすることになった30代フリーター女性を描く軽妙にして心温まる人間ドラマ。
主人公のフリーター女性・ブリジットを演じるケリー・オサリヴァンは、自身が監督した短編映画を除けば、これが長編映画初主演。自らの経験を反映させて脚本を仕上げ、私生活のパートナーでもあるアレックス・トンプソンが監督、プロデュース、編集の三役を担った。タイトルロールの少女フランシスには、オーディションで選ばれたラモーナ・エディス・ウィリアムズ。これが映画デビュー作となった。
34歳になった今もレストランのパート給仕として働いているブリジット(ケリー・オサリヴァン)が、子守の仕事の面接を受けに出かけるところから物語は動き始める。彼女を待っていたゲイの女性カップル(チャリン・アルヴァレス&リリー・モジェク)。彼女たちが養っていたのが6歳の少女フランシス(ラモーナ・エディス・ウィリアムズ)だった。9月に小学校へ入学するまでの約3カ月間、フランシスの子守の仕事を得ることになったブリジットだが、もとより子ども好きというわけでもなく、フランシスともなかなかそりが合わず、トラブル続き。そうこうしていうるうちに、なんとなく関係を持っていた年下のボーイフレンド、ジェイス(マックス・リプシッツ)との間に妊娠が発覚してしまう。
ケリー・オサリヴァンは、女優グレタ・ガーウィグの監督デビュー作『レディ・バード』(2017)に触発されてこの脚本を書き上げたという。そこににじませた子守経験を軸とする自身の経験談は決して明るい美談ばかりではなく、むしろ失敗談の記述が顕著だとしていい。実際、主人公のブリジットは一種のダメ人間で、何かと周囲に苛立ちをぶつけるコンプレックスの塊のような女性。生き方はいいかげん、将来の展望も特になし。ボーイフレンドがいても、好みの年上男性が目の前に現れると、臆面もなく「女」を出し、シッポを振り出す。共感するというより、あきれる観客も少なくないのではないか。
映画の題名だけを眺めると、まるで神々しい幼子でも出てきて人生の教訓を授けそうな気配があるが、これまた聖人のお話でもなく、現人神(あらひとがみ)が誕生する宗教ドラマでもない。フランシスは彼女なりに鬱屈を抱えた少女であり、行動は気ままで勝手放題。当然、ブリジットと衝突する。その果てにフランシスの親たちも巻き込んで、さまざまな「生活の膿み」も明らかになる。
少女とその子守の絆を描く感動作であることは間違いない。ただし、それはダメ女性の精神的再起を描くドラマの一部に過ぎない。年齢こそ34歳になっているヒロインの行動は、どこかティーンエイジャーのそれに近く、ちょっと遅めの思春期映画ともいえるだろうか。有り体にいえば「自分探し」の物語である。
女性の生理、ゲイ・カップルの悩み、望まぬ妊娠など、節々に社会問題もにじむ。街路樹の下で母親がおもむろに乳児に授乳をしようとすると、それが「公衆衛生に反する」と、同じ女性がクレームをつける重いシーンなど痛烈極まりない。しかし、この映画は問題意識に猛ることはついにない。メロドラマへとへつらうこともない。作品のトーンとしてはどこかユーモラスで、意外な表現で喜劇的な処理を施している。そのあたりに製作側の才気を感じずにはいられず、とりわけ自身の過去を反映させながら、安易に私小説の世界におぼれることのなかったケリー・オサリヴァンの語り口、センスは素晴らしい。
この役者兼脚本家は、自分を笑い飛ばす勇気と冷静さを併せ持っている。ドラマの大半を占めているというフィクション性はコミカルな弾みに富み、作り手が十分な客観性を持っていることを証明しているだろう。その大胆さと美しさ。ある意味、グレタ・ガーウィグができなかったことをやってのけており、個人的にはフランスの俳優スザンヌ・ランドンが自ら主演し監督した映画『スザンヌ、16歳』(2020)を連想させる。新しい才能がまた現れた。それを知る喜びがこの映画最大の醍醐味である。
自らを隠さず、美化もせず。そのまっすぐな意志が、澄んだ娯楽精神とあいまって、ただまぶしい。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。