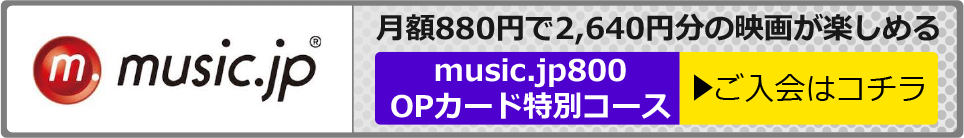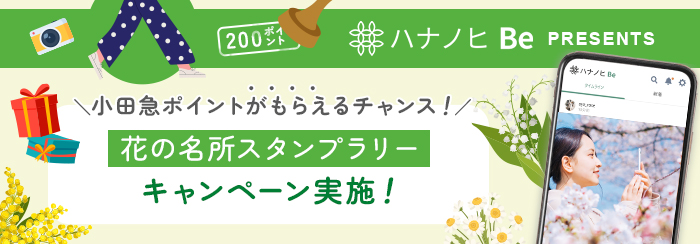特集・コラム
映画のとびら
2022年9月16日
渇きと偽り|映画のとびら #204

 ©2020 The Dry Film Holdings Pty Ltd and Screen Australia
©2020 The Dry Film Holdings Pty Ltd and Screen Australiaメルボルン在住の作家ジェイン・ハーパーが2016年に発表したデビュー小説『渇きと偽り(原題:The Dry)』(ハヤカワ文庫刊)を映画化した刑事ミステリー。幼なじみの不審死の調査に乗り出した連邦警察官が現在と過去、双方に潜む真相に直面していく。アン・リー監督との『ハルク』(2003)、スティーヴン・スピルバーグとの『ミュンヘン』(2005)で国際的になったメルボルン出身のエリック・バナが主演とプロデュースを兼任。監督と脚色はシドニー出身のロバート・コノリー。
メルボルンの連邦警察官アーロン・フォーク(エリック・バナ)のもとへ故郷キエワラから突然かかってきた電話。それは幼なじみルーク(マーティン・ディングル・ウォール)の葬儀への参加を求めるものだった。20年ぶりに戻った故郷は乾燥が進み、かつてアーロンがルークと水遊びに興じた川もすっかり干上がっている。しかし、乾いていたのは土地だけではなく、アーロンを迎える人々の心も同様であった。かつてアーロンは高校時代のガールフレンド、エリー(ベベ・ベッテンコート)の溺死をめぐり、あらぬ疑いをかけられ、逃げるようにして父と街を出ていたのである。アーロンの帰郷を歓迎してくれたのは、幼なじみのひとりであり、かつてルークの恋人だったシングルマザーのグレッチェン(ジュネヴィーヴ・オーライリー)だけだった。そんな中、ルークの父(ブルース・スペンス)と母(ジュリア・ブレイク)はアーロンに息子の死についての調査を依頼する。ルークは妻と小学生の息子を射殺し、自らにも銃を向けた、というのが大方の見立てだったが、父には息子が無理心中をはかるとは到底、考えられなかったのだ。実際、ルークの牧場経営は経済的な破綻を起こしていたわけでもなく、夫婦の不仲がいくらかウワサ程度に伝わってくるのみ。アーロンは若い警官のグレッグ(キーア・オドネル)、ルークの息子が通っていた小学校の校長ホイットラム(ジョン・ポルソン)らの協力を得て調査を進めていったが、やがて彼の中で20年前と今回、両方の変死事件がどこかでつながっているような感覚に襲われるのだった。
物語は、現代の捜査を縦軸に、20年前の回想を折々に絡めて進む。時を隔てたふたつの問題は本当に関係があるのか。故郷にいながらアウトロー同然、それも職務ではなく、個人的な依頼から変死事件の捜査を続ける連邦警察官という主人公の設定も手伝って、映画は観客を絶妙な緊張感に包んで逃さない。
「まだ世界が知らないオーストラリアのリアルを描いた至高のクライムサスペンス」との宣伝コピーを踏まえるなら、干ばつが大きな環境問題となっているのは確かにオーストラリアの現実。主人公にとって潤いがあったのは高校の一時期までで、故郷の干ばつは事件の謎とともに彼の心情を映す鏡としても意味が浅くない。「至高のクライムサスペンス」との表現も持ち上げすぎではないだろう。ただし、ここに派手な娯楽要素は少なく、描写においてこれ見よがしの銃撃戦も猟奇的な流血シーンもない。捜査方法にしても、刑事劇でおなじみの王道の聞き取りと、資料の確認だけ。珍しい証拠検分や特殊能力が登場するわけでもない。終始、抑制を効かせた語り口で、主人公が真相にたどり着くまでの過程を丁寧に追いかけている。
「探偵劇」としてのミスリードも素晴らしい。捜査の流れで浮かび上がる容疑者、信頼ある人間への疑念が無理なく組み上げられ、真相への正しい道筋をほどよくモヤの中に包み込む。よいミステリーとは、どれだけうまく観客(もしくは読み手)を迷走させ、意外性のある謎解きへと導くか、だろう。その点、この作品はゴールへ至る仕掛けがあざとくなく、それでいて、巧妙。とりわけドラマ面では誠実であり、品性すらたたえているといっていい。つまるところ、トリックよりも人間を見つめる目に秀でているのである。
メルボルンの都市から遠い田舎町、そこは因習が支配する村社会。歓迎されない連邦警察官は、閉鎖社会の「箱庭」で、親族問題、借金、虚言、物欲、愛欲、独占欲、ギャンブル欲などのあらゆる人間の「膿み」を目の当たりにする。決して特別なものではない。そんな欲望や負い目は誰の心にだって巣くっている。しかし、それがすべての火種だった。現在と過去をつなぐ鍵だった。言葉にすれば当たり前の、でも、いかんともしがたい人間の業をこの映画はあらためて我々に突きつける。同情にも似たやるせない感情が、怒りすら呑み込む悲壮がラストにせり上がる。静かに、確かに。本当のスリル、醍醐味はそこにあった。
この映画は「人間の弱さ」にスポットを当てている。心の弱さについての物語といっていい。ひどく空虚で切ないエンディングが待っていながら、同時にそれを補ってあまりある豊かな情感も生まれている。ありきたりの刑事ドラマに終わらなかったあたり、やはりオーストラリア映画人たちの努力と才能の勝利といっていい。「渇き」を主題にしながら、巧まずして「渇きを潤す物語」にもなっているのではないか。
諦念にまみれた連邦警察官アーロン・フォークは、一個のキャラクターとしても十分、魅力的。実際、ジェイン・ハーパーは再び彼を主人公に据えた小説『潤みと翳り(原題:Force of Nature)』(ハヤカワ文庫刊)を2017年に上梓しており、2022年9月現在、同じエリック・バナ主演、ロバート・コノリー監督で映画化の真っ最中とのこと。新たな物語に備えるためにも、このりりしい秀作、見逃す手はない。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。