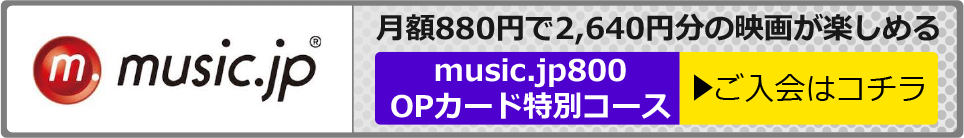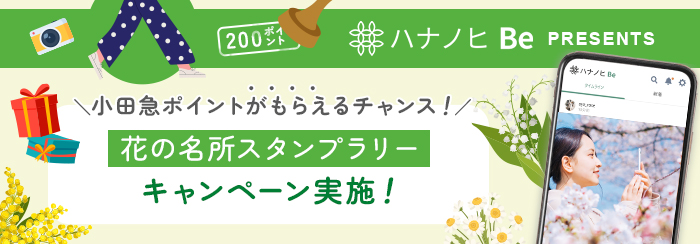特集・コラム
映画のとびら
2022年11月17日
ザ・メニュー|映画のとびら #218

 ©2022 20th Century Studios. All rights reserved.
©2022 20th Century Studios. All rights reserved.『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(2015)、『バイス』(2018)で知られる映画監督アダム・マッケイがプロデュースを務めたユニークなサスペンス。アメリカ北西部の小島に建つ高級レストランへと招かれた客人たちが、世にも奇妙なメニューを目の当たりにする。カリスマシェフ役に『イングリッシュ・ペイシェント』(1996)、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』(2021)のレイフ・ファインズ、彼を怪しむお店の客に『マローボーン家の掟』(2017)、『ラストナイト・イン・ソーホー』(2021)のアニャ・テイラー=ジョイ。監督は、マッケイがプロデュースしたテレビドラマ『メディア王 華麗なる一族』(2018-2021)で注目されたマーク・マイロッド。
アメリカ北西部の小島に向かうため、今、11人の人々が船に乗り込もうとしていた。島に建つのは高級レストラン「ホーソン」。ここには選ばれた人間しか食を許されない。なにしろ、ディナー・コースの料金はひとり1,250ドル。集まったのは高名な料理評論家や映画スター、高慢なIT企業の経営者らの常連客。彼らは店に向かう途中、島で管理される「食材」を紹介され、目を細めるばかり。その中でマーゴ(アニャ・テイラー=ジョイ)は居心地の悪さを感じていた。グルメマニアの友人タイラー(ニコラス・ホルト)に誘われて同行したものの、タイラーはもともと別の女性を誘っており、自分が「代役」だったことを島に入るなり知らされたからだ。店に入ると、そこには料理長スローヴィク(レイフ・ファインズ)に軍隊さながらに率いられたスタッフたちがズラリ。一品目、スローヴィクが客に対して奇妙な口上を始めた。「お願いがあります。食べないでください」。マーゴはスローヴィクにも料理にも最初から冷ややかだったが、何も疑っていなかったほかの客も、3品目が運ばれる頃、何かがおかしいと感じ始めるのだった。
ミステリー調の語り口で進む物語は、美食をめぐる暗い寓話へと転じ、最終的には苦いブラックコメディーとして着地するといっていい。ラストシーンの情景にはさまざまな感想が生まれるだろうが、大半はあんぐりと口を開けたままになるのではないか。アダム・マッケイという映画人の嗜好を知った上で接した人間には当然の展開、後味だろう。一方、何の知識もなくこの映画にふれた観客の中には、すべてが何だったのか、何が起きて何が解決したのか、恐らく全くわからないままの人もいるのではないか。説明描写が徹底している現代映画界では異色の風情であり、その不親切さがまたこの「創作料理」の薬味になっているのも確かだろう。実に、見ている間、どこへ転がっていくか、全く予想がつかない作品であり、その意外性をどこまで楽しめるか、あるいはそれを皮肉めいたユーモアとして享受できるかかが鍵となる。
知的な映画、と評する向きもあるだろう。確かに、料理にすべてをささげているかのようなカリスマシェフ、その決意と客に対する仕打ちには、残酷な一方、抑制された演出と品格が漂う。たとえば、伊丹十三がかつて自身の監督作品で描いたような世俗的な情や欲などはそこになく、コメディーとしても大衆的な笑いにまで変化しない。ただ、アニャ・テイラー=ジョイが演じる「招かれざる客」は正しく一般観客の窓口となっており、彼女の存在があればこそ、この常軌を逸した「美食の密閉空間」はギリギリの線で対象化することができる。エッジな味わいの野心作はいいかげんでヤケクソの奔放作などではない。
レイフ・ファインズ演じる料理長には、ある意味『シンドラーのリスト』(1993)におけるナチス高官と同高位の狂気がにじんでいて、なるほどの配役。拾いものということでは、女性給仕を演じるタイ出身のホン・チャウを挙げていい。彼女の狂気も奇妙だが、表現としてわかりやすく、この作品の鋭くも大胆なトーンへと観客をいざなう引率者となっているだろう。
風刺の効いたレストランの物語といえば、宮沢賢治が著した『注文の多い料理店』(1924年発表)が思い出されるところ。映画『ザ・メニュー』(2022)では客人が食材になることなどないが、別の慄然(りつぜん)とする結末が待っている。美食に酔いすぎることなかれ、ということか。ご注意あれ。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。