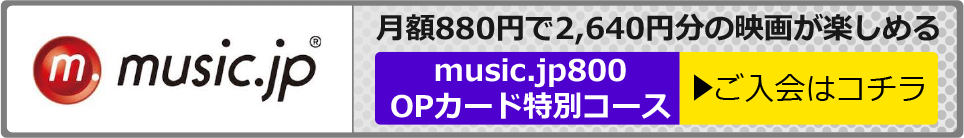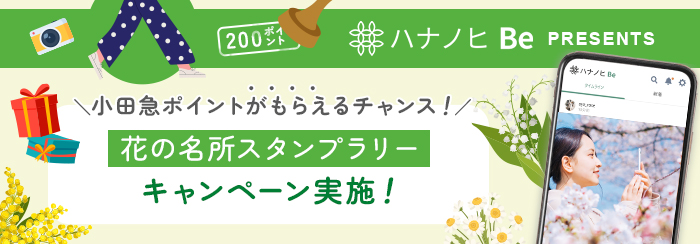特集・コラム
映画のとびら
2022年11月17日
ザリガニの鳴くところ|映画のとびら #219


全世界で1,500万部を発行し、日本でも2021年の本屋大賞で翻訳小説部門の1位に輝いたミステリー小説を映画化。ノースカロライナ州の湿地帯を舞台に、第一級殺人の罪に問われた女性をめぐる切なくも愛おしい物語がつづられる。原作に感動した女優のリース・ウィザースプーンが自らの製作会社「ハロー・サンシャイン」で権利を取得し、テレビドラマ『ふつうの人々(ノーマル・ピープル)』(2020)で注目されたイギリス人女優デイジー・エドガー=ジョーンズを主人公カイアに配し、『ファースト・マッチ』(2018)のオリヴィア・ニューマンに演出を託した。ウィザースプーン同様、原作のファンであるテイラー・スウィフトがこの映画のために新曲《キャロライナ(Carolina)》を書き下ろしている。
1969年、ノースカロライナ州の湿地帯で、ひとりの青年の死体が発見された。彼の名前はチェイス・アンドリュース(ハリス・ディッキンソン)。自動車修理工場の跡取りで、学生時代はアメリカンフットボールの選手として町の人気者だった。近くに建つ見張り台から転落したものと思われたが、事故か殺人かの判断に揺れた結果、警察は幼少期から湿地帯でひとり暮らしを続けている若い女性キャサリン(カイア/デイジー・エドガー=ジョーンズ)に容疑の目を向ける。カイアはその特異な生活ぶりを理由に街の人々から「湿地の娘」と呼ばれ、さげすまれてきた存在だった。拘置されたカイアは、どこか自暴自棄となり、有罪にしたければすればいいと吐き捨てる。それでも、彼女に好意的な老弁護士トム(デヴィッド・ストラザーン)との面会を重ねていくうちに、徐々に自らの過去を明らかにしていくのだった。
殺人容疑をめぐる謎解きの展開、そこからにじむミステリーの味わいがあってこその原作の評価だが、内実は孤独な人生を送ることになった女性をめぐる切なくも美しい人間ドラマである。いかにして彼女は親兄弟から離れ、人里離れたへんぴな湿地で15年もの間、たったひとりで暮らすことになったのか。生活費はどうやってまかなった? 親もなく教育は受けられたのか。何もかもが絶望の気分を誘う。彼女を理解し、庇護しようとした町の人間は雑貨屋の黒人夫婦と、カイアが少女時代に沼地で知り合い、長じて心を通じ合わせる恋人となった青年テイト(テイラー・ジョン・スミス)のみ。このヒロインの境遇に対して、同情の念を抱かない観客は恐らくいないだろう。その人情をくゆらせる部分がミステリーのからくりをゆがめているかといえば、さにあらず。それどころか、謎解きの行方を惑わすミスリードの役割もいつの間にか担っているのである。そのストーリーテリングの妙。やがて始まるカイアの裁判の中で、我々は彼女のえん罪を願いつつ、同時にミステリーとしての毅然とした答えをも期待するのである。
映像化に際して原作者ディーリア・オーエンズの筆致を超えるものがあったとすれば、それは間違いなくデイジー・エドガー=ジョーンズだろう。水辺の素朴な生活を愛し、そこに生息する虫や鳥を愛でて絵に描く「湿地の娘」は、現代人にとって一種の憧憬的存在、あるいは自然そのもの。壊したくない、汚したくない。そのまま手つかずに残しておきたい。そんな、ともすればファンタジー小説、あるいはアニメーションの世界でしか存在し得ないような神秘的にして健気なヒロインを、可憐なるイギリス出身の新進女優は鮮やかに肉体化している。そのみずみずしい存在感。彼女を見ているだけで物語が進む。ワクワクする。ハラハラする。どこまでも応援したくなる。この魅力的な女優を否定的に受け止める観客など、果たしてこの世に存在するのだろうか。役のたたずまいと俳優自身の無垢なる輝きが無理なく重なって、まぶしいことこの上ない。だからこそ、いよいよ謎解きをめぐる疑惑がうねる。なぜ、あの青年は死んだのか、と。
見方を変えれば、これは弱き立場にある女性の戦いの記録でもある。女性心理、生理的感覚に訴えかける部分が確かにあった。原作がやや同性からの人気に傾いているのもそれゆえだろう。「湿地の娘」は「Me Too」時代のひとつの象徴ともいえるかもしれない。そんな共感もきっとある。幸せを願いたくなる。
題名の「ザリガニの鳴くところ」は、原作者の母親が残した言葉に由来している。すなわち、大自然そのものを指すものであり、この作品においては不幸な運命を背負ったヒロインの防衛本能のよりどころになっているといっていい。実際には、ザリガニは鳴かない。でも、鳴き声が聞こえるような場所はあるかもしれない。少なくとも、観客にとって、カイアはその場所そのものである。
ラスト、物語の本当の最後の最後でミステリーは決着する。その瞬間、観客は何を思うのか。恐らく複雑な思いから心のざわめきに襲われるだろう。だが、しばしの後、理解するだろう。彼女が長い間、ずっと心に秘めてきた感情を。心の叫びを。我々観客はザリガニとなって彼女のために鳴きたい。いや、泣きたい。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。