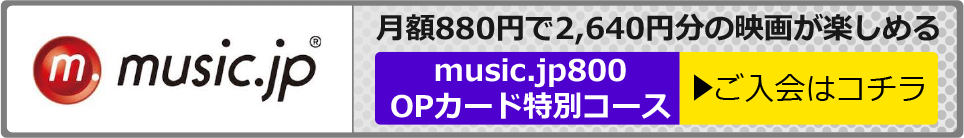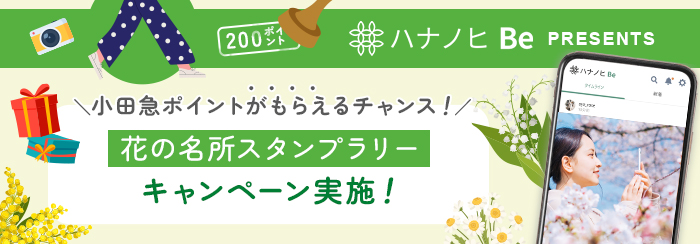特集・コラム
映画のとびら
2022年12月22日
ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY|映画のとびら #224

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

グラミー賞6度受賞を誇る音楽史上最高の歌姫のひとり、ホイットニー・ヒューストンの生涯を追った音楽ドラマ。無垢な幼少期から2012年に48歳で非業の死を遂げるまでの日々が、ライブシーンをふんだんに盛り込みながら感動的につづられる。ホイットニーを演じる大役を担ったのは『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』(2019)のジャナ役で注目されたナオミ・アッキー。レコード会社のプロデューサー役に『プラダを着た悪魔』(2006)、『キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー』(2011)のスタンリー・トゥッチ。ホイットニーの夫ボビー・ブラウン役に『ムーンライト』(2016)のアシュトン・サンダース。ホイットニーのソウルメイト、ロビン・クロフォード役に『ヘルウォーク』(2017)のナフェッサ・ウィリアムズ。監督は『クリスマスの贈り物』(2013)のケイシー・レモンズ。
ホイットニー・エリザベス・ヒューストン(ナオミ・アッキー)の音楽キャリアは11歳のとき、生まれ故郷ニュージャージー州ニューアークで聖歌隊に入ったことから始まった。モデル活動と並行して母シシー(タマラ・チュニー)のバックシンガーを務める中、ある日、音楽プロデューサー、クライヴ・デイヴィス(スタンリー・トゥッチ)に見初められ、レコード会社アリスタと専属契約。初出演のテレビでの歌唱で視聴者の耳を釘付けにする最高のスタートを切った。21歳でファーストアルバム『そよ風の贈りもの』をリリース。7曲連続でシングルチャート1位に輝く成功をものにする。私生活では寄宿学校時代に知り合ったロビン(ナフェッサ・ウィリアムズ)と同性愛的関係を続け、その一方でボビー・ブラウン(アシュトン・サンダース)と恋に落ち、結婚。だが、ボビーはホイットニーに忠節を誓う夫ではなく、さまざまな心労が重なる中、彼女はドラッグに溺れていくのであった。
ホイットニー・ヒューストンといえば、やはり映画『ボディガード』(1992)における挿入歌《オールウェイズ・ラヴ・ユー》(作詞・作曲:ドリー・パートン)の大ヒットが大きい。14週連続で全米シングルチャート1位の座を譲らなかった同曲で、彼女の声は大衆認知を絶対的にしたといっていいが、同じ年にボビー・ブラウンと結婚もしているのである。つまり、キャリアのピークを極めたと同時に、人生の下り坂を歩み始めたという次第。この映画は奇跡の声を宿した黒人女性の成功物語であり、同時に不運と不遇にまみれ自らを見失ったアーティストの転落劇である。輝かしい実績と歌声の奥底で、彼女は何を求めていたのか。何を訴えようとしていたのか。光と闇の中で明滅する歌姫の笑顔が痛ましくも美しい。
この映画最大の特徴は何かといえば、やはりソウルメイトであったロビン・クロフォードを登場させた点にあるといっていい。かつてケヴィン・マクドナルドの監督で記録映画『ホイットニー ~オールウェイズ・ラヴ・ユー~』(2018)が製作されているが、実に綿密にインタビュー素材を組み上げた同作品において、最後まで獲得できなかったのがロビンの証言だった。ある意味で家族以上にホイットニーを身近で見ていた彼女をしっかり描くことで、今回の劇映画は歌姫の内面に肉迫しようとしている。その野心にふれる一点においても大いに見る価値のある評伝映画といえるだろう。
歌唱場面においては、ほぼホイットニー自身の歌声をそのまま生かしている。その迫力、美しさはスクリーンにおいても健在で、むしろ今回の映画ならではの音響処理によって広がりと深みを増した部分もあるかもしれない。場面によってはライブの記録映像にふれているような錯覚も起き、予期せぬ高揚感に襲われる瞬間がある。無論、ホイットニーを演じたナオミ・アッキーのパフォーマンスも賞賛されるべきで、容姿としてさほど近いとは思えないものの、気づかぬうちに彼女のパフォーマンスに魅了されている観客も多いのではないか。少なくとも、下手なモノマネには終わっていない。
脚本担当は『ボヘミアン・ラプソディ』(2018)のアンソニー・マクカーテンで、ドラマ的にはかなり近い印象を持つ観客が多いだろう。ビギナー向けに接しやすい作品構造になっており、クライマックスからラストへかけての処理にはホイットニーへの同情にも似た感動が湧き上がる仕掛けが施されている。彼女が流す涙にほだされる観客は少なくないだろう。彼女を古くから知るファンなら、才能が道半ばで失われてしまった悔恨の反動として、その歌声にあらためて接してみたいという欲求が駆り立てられるはず。一方で、ホイットニーになじみのなかった観客には、彼女の歌曲への意味深いガイドとなったといっていい。
不世出の歌姫はまたここから新たな歩みを始める。もう一度、その魂が輝き始める。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。