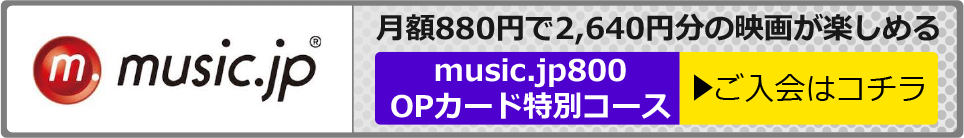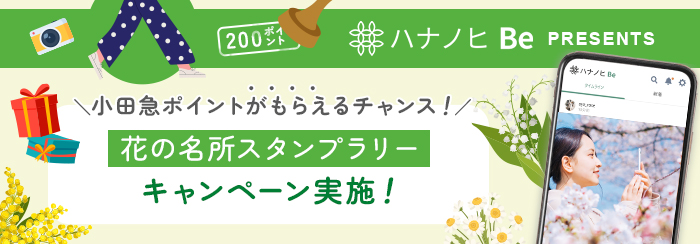特集・コラム
映画のとびら
2023年1月12日
そして僕は途方に暮れる|映画のとびら #226

 ©2022映画『そして僕は途方に暮れる』製作委員会
©2022映画『そして僕は途方に暮れる』製作委員会2018年に上映された同名舞台劇を、同じKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔主演で映画化したコメディー。追いつめられるとすぐに逃亡を企ててしまうフリーターの当て処もない旅を追っていく。舞台版の演出を担っていた三浦大輔が映画版の監督も担当。同じく舞台版に引き続き、前田敦子が主人公の同棲相手役を、中尾明慶が主人公の友人役を務めている。姉役に香里奈、母親役に原田美枝子、父親役に豊川悦司。
フリーターの菅原裕一(藤ヶ谷太輔)は、同棲して5年になる恋人・里美(前田敦子)とグズグズの関係を続けていた。朝、会社に出かけていく里美を見送ると、けだるそうにベッドから起き上がり、スマホをいじり始める。夜、新宿に出た裕一が待ち合わせていたのは白いコートを着た女性だった。その彼女と肩を並べて街へと消えていく裕一は、なぜか何度も来た道を振り返る。何事もなかったように帰宅した裕一だったが、里美は「ガマンできると思ったけどできないから言うね」と、おもむろに声をかけるのだった。「今まで女の人と会っていたんでしょ? 話し合いたいの。その人とはどういう関係なの!?」。里美の大声にたじろいだ裕一は、おもむろに部屋にあった服をバックパックに詰め始めると、「急に体調が……。どうしたんだろう」などとうそぶき、よろめきながら、アパートから夜の街へと飛び出していくのだった。
主人公の頼る術はスマホだけ。そこに登録された人間を順番に頼っては、同じように居場所を失って逃亡を繰り返す。近しい友人(中尾明慶)の部屋に転がり込んだかと思えば、バイト先の先輩(毎熊克哉)、映画業界で働く後輩(野村周平)、姉(香里奈)、ついには故郷・北海道の母親(原田美枝子)、父親(豊川悦司)にまで逃げ場を求める。甘えの限りを尽くす自堕落男の、およそ1カ月半に及ぶ逃亡の物語は、節々にクスッとする笑いをにじませて、その「終着地」まで観客を案内していく。
都合が悪くなると逃げ出すという主人公の行動は、確かにクズといえばクズ。そのどうしても「問題」に正面から対処できない「性癖」に観客は笑いを引き出されるわけだが、見方を変えればそれはこの主人公ならではの「危機に対する防衛本能」の表れともいえるわけで、その意味では決して縁遠いものではない。むしろ、誰もが抱える意志薄弱、逃避行動のドラマともいってよく、自身の姿を菅原裕一に重ねる観客も少なくないのではないか。身につまされる喜劇、というべきだろうか。多かれ少なかれ、我々は逃げている。どこかそういう日常を過ごしている。それを静かに見つめている目がこの映画にはある。
観客が主人公に自身を見る一方で、物語の中で裕一自身がおのれを見る鏡のような存在こそ、豊川悦司演じる父親だろう。10年前、家族を捨てて逃げていったこの父親こそ、裕一の原点であった。その父親との「対決」もまた、男児としての普遍的な物語だといっていい。そういう骨太な「幹」がこの映画には確かにある。それがとりわけ美しい。りりしい。やはり、「枝葉」のドタバタ笑いに終わっているわけではない。
舞台での活躍が麗しい三浦大輔という演出家は、自作の映画化を今日まで数度、繰り返してきた。いずれも秀作の誉れに高いが、人間の微妙な感情をささやかに刻みつつ、劇的な高揚感がクライマックスに向けて緊密に組み上げられている点で、今回の作品はこれまでの最上位に位置しているといっていい。おかしゅうて、やがて哀しき我が身かな。自身をきっちり笑いに昇華できているあたり、お見事である。
藤ヶ谷太輔はその整った容姿から出演作に「王子キャラ」ともいうべきキラキラ作品も少なくなかった。時に鼻水を垂らしながら人間の弱さを演じきった今回は、その意味で転機ともいうべき仕事であり、新たな俳優人生の始まりを告げる一本となったといっていい。
脇では、クズ中のクズ、まさに「人生のクズ王」ともいうべき父親役の豊川悦司が素晴らしい。前田敦子、中尾明慶も堅調。母親役の原田美枝子、姉役の香里奈もほどよく人間くさい。いいかげんな先輩役の毎熊克哉に加え、なぜか裕一を英雄視する助監督役の野村周平は物語のいいガス抜きとなった。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。