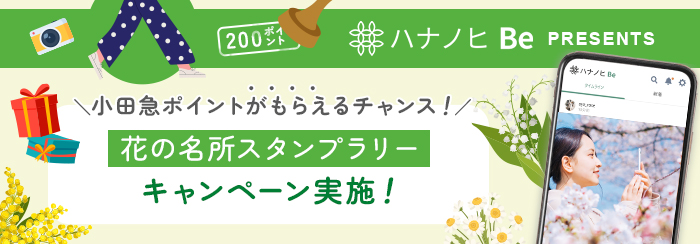特集・コラム
映画のとびら
2023年3月2日
メグレと若い女の死|映画のとびら #240

 ©2021 CINÉ-@ F COMME FILM SND SCOPE PICTURES.
©2021 CINÉ-@ F COMME FILM SND SCOPE PICTURES.フランスで絶大な支持を得るベルギー出身の作家ジョルジュ・シムノンが1929年に創造した人気キャラクター、メグレ警視を主人公にした刑事ドラマ。1954年に刊行された同名長編を原作に、変死を遂げた若い女性をめぐる意外な真相を描いていく。メグレに扮するのは、今年75歳を迎えるベテラン俳優ジェラール・ドパルデュー。監督は『髪結いの亭主』(1990)のパトリス・ルコント。
ある土曜の夜、モンマルトルの公園で象牙色のドレスを着た若い女性(クララ・アントゥーン)の変死体が発見された。ドレスこそシルクの高級品だが、それ以外の所有物、着用物は皆、不釣り合いな安物ばかり。体には5カ所の刺し傷がある。犯人が左利きであることだけが確認されたが、それ以外は被害者の身元も何もかも不明。警視庁犯罪捜査部のジュール・メグレ警視(ジェラール・ドパルデュー)が事件の背景を探ると、被害者と同居していた女性ジャニーヌ(メラニー・ベルニエ)の存在が浮かぶのだった。
1950年代のパリを舞台にした殺人ミステリーは、しっとり、ロマンティックに展開するかと思えば、さにあらず。どちらかといえばスピーディーで、どんどん先へお話が進んでいく。矢継ぎ早に証拠が提示され、事件にかかわる人間が次々に登場するので、ボンヤリしていると置いてきぼりをくってしまう観客もいるかも。裏返せば、それだけ密度の濃い仕上がりの作品ともいえるわけで、89分という上映尺にほとんどダレ場がない。登場人物を見渡しても動きが鈍そうなのはドパルデューによる巨体メグレだけだが、そのドパルデューの巨漢ぶりは原作にあるメグレのイメージそのまま。チャールズ・ロートンやジャン・ギャバンが演じたメグレが脳裏に焼き付いている往年の映画ファンはもちろん、小説ファンにも安心して見られるだろうし、一方で現代の若い観客には短いカッティングで映像をつなぐ話法が心地いいのではないだろうか。人気漫画『名探偵コナン』の目暮十三刑事が好きな人ならさらに大丈夫。
パトリス・ルコントの側から見るなら、すでに『仕立て屋の恋』(1989)でシムノン文学に取り組んでいる過去があり、その点においても原作ファンの信用は厚い。それでなくとも、ルコントはシムノン作品の熱心なファンであり、だからこそ名作の誉れ高い『メグレと若い女の死』の映画化に際してはいよいよ無駄口をきかない作品作りが徹底されたといっていい。同じ監督の『髪結いの亭主』みたいな、オシャレでコミカルな気分を期待する観客はちょっと要注意。
メグレの物語というと、もちろん「ザ・推理」の世界。タッチとしては戦前のミステリー作品のムードに近い。機関銃をぶっ放すような派手なギャング映画からはほど遠く、毒殺や刺殺の事件が中心。すなわち、犯人や被害者の動機や背景を探っていく過程が大きな見どころで、テンポの速い展開が施されているとはいえ、今回も古典絵画を味わうような気分で接することを勧めたい。
陰影に富んだ映像もこの作品の大きな特徴。これだけ闇の描写が多いルコント作品もなかなかない。ドパルデューもほとんど笑わず、見事なほど無愛想。『仕立て屋の恋』の主演俳優ミシェル・ブランといい勝負である。結果、メグレがたどり着く真相もぐっと哀感を漂わせた。謎解き描写に手抜かりはないのだが、この映画の場合、事件解決後の余韻の方が一層渋く、味わい深いのではないだろうか。そこには、どうしようもない人間の業があり、パリを往来する人間たちの隠された「素顔」がある。パリという都会が抱える問題は、現代日本のそれとも遠くない。そんな社会性の側面からこの物語を楽しむことも当然、可能である。
ルコントはエンディングでもユニークな「メグレ描写」を敢行している。肝いりのシムノン・ファンならではのメグレ愛といっていいが、ある意味、事件の結末以上に切ない。ルコントの真意としては「もっとメグレを!」といったところか。そんな心理のひだを考察するのもオツである。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。