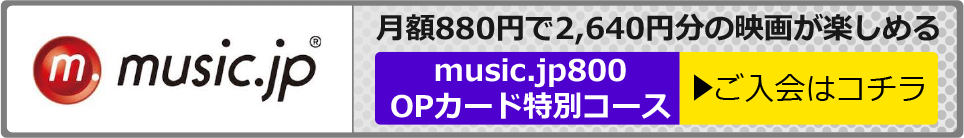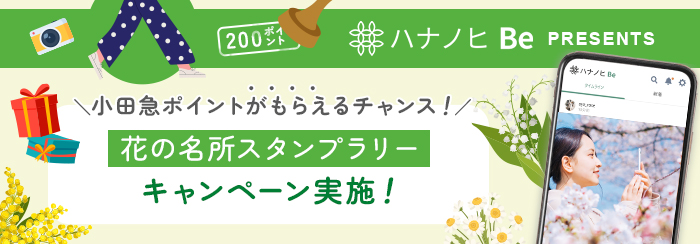特集・コラム
映画のとびら
2021年6月18日
海辺の金魚|映画のとびら #122【小川紗良監督・単独インタビュー】


撮影現場で撮影映像を確認している小川監督 ©2021 東映ビデオ
――どのように始まった企画だったのですか。
小川:2019年の夏に撮影した作品で、企画が始まったのがその半年くらい前の2019年3月頃です。今回、主演してくれた小川未祐さんは私が学生時代に撮った短編映画『最期の星』(2017)にも出てくれているんですけど、彼女と久しぶりに会ってお茶をしたときに、将来のことや仕事のこと、18歳なりに葛藤していることをいろいろ話してくれて、その姿がすごくいいなって。また彼女と映画を作りたい、小川未祐さんありきで映画を撮りたいという感じでスタートした感じです。
――製作に当たって、何か決め事みたいなものはあったのでしょうか。
小川:私の場合、映画を作るきっかけは個人的な思いだったり、些細なことだったりするんですけど、それを自分だけの世界に閉じないで、できるだけ社会に対して開けた作品にしたいという気持ちがあります。今回、身寄りのない子どもたちを描いているのも、その理由のひとつです。ただ、個人的だからこそ普遍的になることもあると思うので、両方のバランスを大事にしたという感じですね。テーマとしてはひとりの女の子が自分の人生を歩み出していく瞬間を描こうというのが最初にあって、児童養護施設というのは入所者が18歳で自立することが多い。そういう状況を間近に控えた女の子ということで、ちょうど18歳だった小川さんでできないかなというのもありました。私自身、さまざまな境遇に置かれた子どもたちを描いた作品をいろいろ見てきたというのも大きいです。

主人公・花を演じる小川未祐(左)とロケ現場にて
――たとえば、どんな作品を?
小川:『キャンディ キャンディ』は漫画(1975-1979)も読んでいましたし、アニメーション(1976-1979)も見ていました。あと、小さい頃、『明日のナージャ』(2003-2004)というアニメーションもテレビで見ていましたね。どちらも孤児院で育った女の子が主人公の作品です。映画だと、是枝裕和監督の『誰も知らない』(2004)はもちろん、最近では『ショート・ターム』(2013)、『悲しみに、こんにちは』(2017)が印象に残っています。ドキュメンタリーでも『隣る人』(2011)、『さとにきたらええやん』(2016)、『沈没家族 劇場版』(2018)などたくさん見てきました。そういう関心が今回の映画に結びついたところはあるかと思います。
――脚本はスムーズに進みましたか。
小川:いえ、全然(笑)。すごく大変でした。初めての長編ということもあって、単純に尺も長くなるし、かかわる人の数も増えるので、あらためていろんな本を読んだりして脚本の勉強をしました。プロデューサーとも何回も話し合いましたし、20回くらい書き直して、その過程で話も大分、変わりました。「施設で育った女の子の自立」という部分はずっと変わらなかったんですけど、(主人公の高校生・)花(小川未祐)の周りの人をどれくらい、どうやって出していこうかと悩んで、最終的にたどり着いたのは、施設に新しく入所してくる晴海(8歳の少女/花田流愛)と花、ふたりの物語にすることでした。
――花にとって、晴海というのは、どこか自分を映す鏡になっていますね。
小川:かつての自分であり、これから自分のようになる人間です。もうすぐ自立をしようとしている花にとって、晴海は過去を振り返り、未来も考えるきっかけになるんですね。ふたりの関係に物語の舵を切ってからは、晴海を通して花がだんだん浮かび上がっていくような手ごたえも出てきて、物語も動いていったなという感じです。

――この映画の大きな特徴は、全く説明的ではないところです。物語や設定に余計な説明を加えない。観客を甘えさせない。ある意味、不親切ですらある。そこに小川紗良という監督の気骨を見ます。とても潔いです。
小川:どこまで見せて、逆に何を見せないかということは脚本の段階でかなり悩みました。花が母と実際に面会するシーンも書いてみたり、母からの手紙を読むシーンを入れたり、いろいろなことをしたんですけど、花自身も母親のことはわからないし、実際に母親に何があったのかもよくわかっていない。そもそもそれだけ母との距離があったわけで、それなら母とのこともあれこれ書かずに、子どもの視点……花と晴海の視点に寄り添ってやってみようと。私自身、説明しすぎない作品が好きというのもありますけど、「やりすぎない」ということには注意してやっていたと思います。今、作られている映像作品っていろんな情報にあふれすぎているとも感じていて、もっと見る側に想像をさせたり、解釈の余白を持たせたりする作品にしたいなという思いはありました。

――冒険的な映画ともいえます。
小川:この映画の作り方自体が冒険的だったかもしれません。小川未祐さんとまた映画を作りたいという一心で始めていますから。誰かに依頼されたわけでもないですし、規模が小さいにもかかわらず、近くの千葉や神奈川ではなく、鹿児島までスタッフを連れて行きましたからね(笑)。鹿児島県阿久根市(での撮影)にこだわるわりに、製作費は撮影中でも集まりきっていなかったですし、配給も決まっていなければ、上映先も何も決まっていなくて、それなのに突っ走っていたんですよね。そこはプロデューサーの小出大樹さんをはじめスタッフの方々、阿久根市の方々、本当にありがとうございました、すみません、という感じです(笑)。子どもたちに関しても冒険でした。(職業的に活動している)子役ではなく、(施設の出演者は皆)地元の子どもたちでしたので、それもかなりのチャレンジだったと思います。

スタッフ、小川未祐(中央)と打ち合わせ
――阿久根市にご自身のルーツがあるとか。
小川:そうです。小さい頃からゆかりのある場所で、観光大使もやっていて、学生のときに作った中編作品も阿久根市で撮っています。そこでしか撮れない風景があるし、何より人の魅力ですね。中編を撮ったことでいろんな人とのかかわりができました。
本当に熱のある面白い人たちがいっぱいいるんです。映画って人の縁でできていくものだと私は思っていますので、いい人たちと撮りたいなという思いが最初からありました。。
――半ば、自主映画的なこだわりで出発をしたものが幸運にも商業デビュー作となった、ともいえます。
小川:結果的に商業作品になりましたけど、作り方は今までの自主製作の作品と地続きというか、顔の見える関係性の中、手探りで作ったという印象です。小川未祐さんと再会した当初は短編でやるつもりだったんですけど、話を書いていく中でどんどんふくらんでいってしまって、「これは短編では無理だな」と思って、そこからいろんな人を巻き込み始めたっていうのが真相ですね(笑)。
――長編作品になったとはいえ、最小単位の人間関係と、最短距離での物語の展開で仕上げています。76分という尺からも明らかなように、無駄が少ない。その一方で、題名は示唆的です。主人公の花を金魚に見立てているわけでしょう?
小川:「金魚」については、ご覧になる方によって解釈が異なりますね。今の作品タイトルはプロデューサーと話し合っていく中で出てきたものですけど、「海辺の金魚」という言葉が出てきたところで、私の中でも軸ができたといいますか、作品が見えてきたところがありました。この矛盾をはらんだタイトルこそ、この作品を表しているなって。タイトルが決まってから、(劇中に登場する)金魚をどう使うかを考え直したというところもあります。
――このタイトルも含め、実にとんがっている作品といえます。可愛らしい思春期の女の子の話かなと思って油断していると、ビッと切れそうな鋭さ、危うさがあります。ある意味、怖い映画でもありますね。小川紗良という人の本性を目の当たりにするような。
小川:そうかもしれません(笑)。少なくとも、万人受けする映画ではないですね。突き抜けて明るいわけでもないですし。でも、ご覧になる人によっては救いになったり、世界を肯定できたりするものにもなっているのかな、とも思っていまして、そういう人がひとりでも観客の中から生まれたらうれしいな、と。

――『人魚姫』の話を劇中で引用しているのも、金魚という部分との兼ね合いでしょうか。陸の世界に上がって海に戻れないお姫さまのお話はずいぶん象徴的です。
小川:金魚も大昔は自然の中にいたと思うんです。でも、人間の手の中で観賞魚として退化していって、自然に帰れなくなった。人魚姫も不完全な形で人間界に行って、海にも戻れず悲劇を迎えてしまう。もともと『人魚姫』のお話が好きというのもあったんですけど、今回のお話と重なるところがあるなと思って入れました。
――花は金魚鉢の中の金魚を眺め、施設にやってきた晴海と接し、両者に自分を投影した結果、それぞれをそれぞれの「金魚鉢」から解き放ちたいと考えるようになる。メタファーとしての金魚がやがて実感を伴っていく流れが秀逸です。
小川:子どもや女の子って、大人になっていく中でいろいろな「呪い」=自分をしばるものを感じていると思うんです。そういうものを、この物語の中で少しでも解いていくことができたらいいな、と。なんだか「祈り」のような気持ちで作っていた部分もあります。

――そういう点では女性目線がしっかり映えている。思春期映画であると同時に、「女性映画」というカテゴリーに分けてもおかしくない色合いの作品です。
小川:やっぱり自分も女性ですし、女の子の話を撮ったわけですから、自然とそうなったんだと思います。女の子たちへの祈りを込めていることは確かです。とはいえ、「女性映画」とカテゴライズするよりは、「私たちの映画」と言うほうがしっくりくるような気がします。
――山崎裕さん(『誰も知らない』『歩いても 歩いても』『永い言い訳』)を撮影技師に招かれているのは、ドキュメンタリー・タッチといいますか、あまり芝居の臭みを感じさせない「画(え)」が欲しかったということでしょうか。
小川:私がドキュメンタリー性のある作品が好きというのもありますけど、子どもたちがいっぱい出てくるので、そこを自然に撮ることができたらいいな、と。やっぱり山崎さんは子どもを魅力的に撮られる方だという印象がありますね。(カメラマンを誰にと考えたとき)真っ先に浮かんだのが山崎さんでした。でも、さすがに巨匠過ぎるなと最初は躊躇したんですけど、ダメ元でお願いしました。それも冒険でしたね(笑)。
――音楽担当は渡邊崇(『ぼくたちの家族』『浅田家!』)さんです。この人、感傷に溺れるタイプではありませんね。お涙頂戴やおセンチが大嫌いな人。この人選にも監督・小川紗良のこだわりを感じます。
小川:効果整音の高木創さんの紹介でした。ストレートに感動をあおるようなことはされない方ですね。私もそういうことはしたくないと思っていて。音楽の使い方っていろいろあると思うんですけど、今回は音楽が作品世界をそっと支える基盤になってほしかった。渡邊さんにはその意図を汲み取っていただけました……というか、それ以上のものを私に返してくださった感じですね。本当に感動しました。

音楽教室の場面を演出中
――処女作には、その監督のすべてが出るといわれますけれど、いかがでしたか。
小川:どうなんでしょう。でも、商業長編の一作目が自分のオリジナル脚本で、しかも自分が信頼できる方々と好きな場所で作ることができたなんて、本当にぜいたくなことです。同時に、こういう作り方ができてよかったなっていう思いもあります。
いろんな方のデビュー作のお話を伺うと、「なかなか自分の意見が通らなかった」みたいなご苦労をよく聞くんですけど、今回はこんな駆け出しの未熟な人間にみなさん対等に向き合ってくださって、本当に恵まれた現場だったなって思います。いろんなラッキーも重なって、奇跡的にできた作品ですね。
――もしかしたら、本当の苦労はこれから始まるのかもしれません。
小川:そうかもしれません。作品の規模が大きくなるにつれて、いろんな制約も出てくると思います。けれど、私としてはできるかぎり顔の見える関係性の中で、新しい人ともコミュニケーションを重ねて作っていきたいなって思っています。映画に関心がない人がひとりいるだけで、その空気は少しずつ現場で伝播(でんぱ)しますから。私も役者としていろんな現場を見てきていますので、スタッフひとりひとりの思いがどれだけ作品に影響を与えるかはよくわかっているつもりです。
――小川さんは作家としてウソをつきたくないタイプでしょう?
小川:はい、そうですね(笑)。
――そのこだわりは美しい反面、それゆえに次回作の発表がずいぶん先になってしまったら、それはそれで寂しいです。
小川:でも、たとえば是枝監督は作家性を保ちながら広く伝わる豊かさのある作品をずっと作り続けられています。その背中を見ている人間としては「不可能なことではない」という希望を感じているんです。なんとかめげずにやっていきたいし、やっぱり映画作家でありたいなって思っています。もちろん、作品が(観客に)届かなければ意味がありません。しかも、国内だけでなく、文化や言語の違う場所の人にも届くような。そういう普遍性は常に持ち続けていきたいですね。作家のものでありつつ、同時に、開けた作品を作りたいです。
――その姿勢は「日本映画を閉じ込めない。外の世界に持っていけるようにしたい」という、小川さんの以前から変わらぬ意志の表れですね。
小川:先日のアカデミー賞も女性の監督(『ノマドランド』の)が受賞されたじゃないですか。本当に素晴らしい作品や作家が世界のいろんな国から出てきているので、そこに負けずにいたいという気持ちはあります。最近では、韓国映画の『はちどり』(2018)や『夏時間』(2019)にも刺激を受けました。

――監督・小川紗良はどこへ行くのか。たとえば、小川未祐という女優をミューズとして、作品を重ねていく方向もあったりするのでしょうか。
小川:彼女は魅力的です。役者さんとしてもそうですけど、人間としての感性もいいし、ダンスや歌もやりたいという欲求も持っている。そういう個性をこれからも追いかけていきたいという思いはあります。
――フランソワ・トリュフォーでいうところのジャン=ピエール・レオーですかね。
小川:そうなったらすごくうれしいです。阿久根でもまた撮りたいですね。大林宣彦監督の「尾道三部作」とか大好きですから。みなさんがついてきていただけるかどうか、わかりませんけれど(笑)。単純に、遠くへ行きたい人間なんですよ。役者としても地方ロケが大好きですし、旅も大好きなので。非日常的な場所で感性が動かされるのが好きなんです。海外もいいですね。あ、台湾で撮りたいです(笑)! そういう希望が叶うように、これからもがんばって、いい作品を作っていくことができたらと思います。

1996年、東京都出身。『イノセント』(2016)で映画初主演。同年、短編『あさつゆ』で監督デビューを果たし、以後、役者、映像監督、文筆家など、多彩な創作活動を展開。早稲田大学在学中には是枝裕和監督の講義を受講。テレビドラマの代表作に『まんぷく』(2019)、『アライブ がん専門医のカルテ』(2020)、『名建築で朝食を』(2020)、『ディア・ペイシェント 〜絆のカルテ〜』(2020)など。映画の出演作に『聖なるもの』(2018)、『ビューティフルドリーマー』(2020)など。『海辺の金魚』(2021)で長編映画監督デビューを飾った。役者としては短編映画製作プロジェクト『DIVOC-12(ディボック・トゥエルブ)』が公開待機中。
 ©2021 東映ビデオ
©2021 東映ビデオ最近では本広克行監督の学園ドラマ『ビューティフルドリーマー』(2020)に主演するなど、いよいよ俳優として目覚ましい活躍を見せ始めている小川紗良が長編監督デビューを果たした。児童養護園で暮らす18歳の少女、その揺れる心を繊細かつ大胆に切り取っている。
鹿児島の児童養護園「星の子の家」に、8歳の少女・晴海(花田琉愛)が入所してきた。母親と距離を置くことを余儀なくされ、殻に閉じこもる彼女を、最年長入居者の花(小川未祐)はかつての自身の姿に重ねて、なにかと面倒を見ていく。もっとも、そんな花自身も高校3年生となり、卒業とともに養護園を出なければならないという微妙な時期にさしかかっていた。時折、思い出されるのは、とある事件で長く刑務所に収監中の母親(山田キヌヲ)のこと。晴海とはまた別種の、心に消しがたい痛みを花は抱えていたのだった。そして、夏のある日、花は突然、弁護士から母との面会を提案される。
養護園の生活空間を軸に、女子高生とその周囲の人間のふれあいを描く物語は、一見、ありふれた日常ドラマに映るが、わかりやすい思春期映画や人情劇を期待すると少々、面食らうだろう。説明的な描写がほとんどなく、ナレーションのたぐいも加えない。進学や恋愛をめぐるエピソードが出てきても「きっかけ」や「さわり」を見せる程度。母親や晴海についての事情や真相も「連想」はさせても明快なゴールはない。諸事が観客の解釈にゆだねられているといってよく、作品に対して受け身のままでは何の感動も得られず、あっけない読後感に終わってしまうのではないか。裏返せば、積極的にこの語り口に真向かい、物語に参加しようとすればするほど刺激的な作品へと印象が変わるわけで、その意味では我々は試されているといえる。そう、この作品は見る人間を甘えさせない。過保護にしない。そのりりしさ、スリル。
題名にある「金魚」とは、直接的には花、もしくは晴海であり、見方によっては養護園の子どもたち、転じて今に生きる人たちすべてのメタファーでもあるだろう。タイトルバック、金魚鉢の中の和金とそれを見つめる花の姿は象徴的だ。きっと誰もがそれぞれの金魚鉢を持っている。金魚鉢のような囲いの中で生きている。その生活にとどまっている。物語に踏み込むことができた観客は、人生という金魚鉢をのぞき込み、鉢の外へと泳ぎ出そうとするのである。そんな気分など、ちょっと文学的でもあったりする。
田中絹代が『恋文』(1953)で監督進出を果たしたのは44歳のときだった。アイダ・ルピノが監督業に手を染めたのは31歳のときのこと。小川紗良、今年25歳。俳優と監督、それぞれの道を並行して歩んでいるあたり、『レディ・バード』(2017)、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)のグレタ・ガーウィグとちょっと似ている。ガーウィグの監督デビューも25歳だった。ただ、小川紗良はガーウィグほど「おしゃべり」ではない。本人も作品も無駄口が少ない。ドキュメントと虚構の狭間で人間の真情に迫ろうとした尽力もふくめ、その野心的な創作姿勢には早くも独自の個性が輝いている。表現者として今後どう進化していくのか。その行く末を見届けるのも、この映画の観客の務めだろう。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。
人気記事ランキング
最新情報