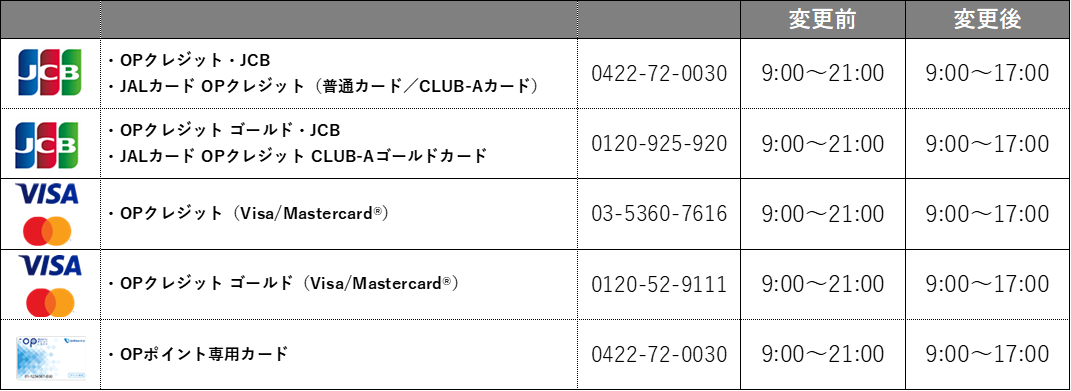特集・コラム
映画のとびら
2023年3月31日
逃げきれた夢|映画のとびら #248(最終回)

 ©2022『逃げきれた夢』フィルムパートナーズ
©2022『逃げきれた夢』フィルムパートナーズ第20回東京フィルメックスで新人監督賞グランプリを受賞した人間ドラマ。瀬々敬久監督をはじめとする厳しいシナリオ選考を勝ち抜き、映像化への道をつかんだその監督は『枝葉のこと』(2017)、『お嬢ちゃん』(2018)の二ノ宮隆太郎。主演を務めるのは、二ノ宮がかねてよりファンを公言している光石研。ここでは、光石自身の人生経験を反映させつつ、とある高校教師の日常を描いていく。主人公のかつての教え子に吉本実憂。妻に坂井真紀。親友役にプライベートでも光石と懇意の松重豊。
北九州市。とある介護施設を訪れたのは末長周平(光石研)である。車椅子に座る父親(光石禎弘/光石研の実父)に「いやあ、参ったよ。どうしようかね、これから」と話しかけても、父は何の反応も示さない。場面は変わって周平の家。ベッドで呆然と座っていた周平が階下に降りると、居間には娘の由真(工藤遥)がいた。「おはよう」と声をかけても、さえない返事しかない。一方、妙に明るく接する父親に娘は「気持ち悪い」とつぶやく。妻(坂井真紀)の姿はもう家になかった。周平は定食屋で昼食をとる。周平はここで日替わり定食を食べてから仕事に向かうのを日課にしていた。周平の仕事は定時制高校の教頭だった。定食屋で給仕をしているのは元教え子の平賀南(吉本実憂)である。食べ終えた食器を南が片づけると、周平はコートをはおり、会計をすることなく、そのまま外へ出て行った。その後を南が追う。「先生、お会計」「あ、払っとらんかったかね。ごめん、ごめん」。慌てて財布から千円札を取り出すも、ピタッと手が止まる。周平は南を見つめておもむろに話し始めた。「俺、病気なんよ。忘れるんよ……」。そう言うと、紙幣を南に渡すことなく、去っていった。周平は父と同じ記憶が薄れる病に冒されつつあったのである。
徐々に記憶が薄れていく定年間近の教師。そこから起こるささやかな感情のさざ波、周囲とのひずみ。そのくくりでこの物語をとらえるなら、一種の難病ものだろう。記憶を失うことは自我の喪失であり、当人にとっては死も同然。「これまで」と「これから」という自省、課題がのしかかる。
黒澤明作品でいえば『生きる』(1952)である。若年性アルツハイマーを扱った渡辺謙主演の映画『明日の記憶』(2005)を連想する向きもあるだろう。しかし、光石研が演じる教頭は「生き直す」ために奮起することもなく、病気との闘いに情熱を傾けるわけでもない。ただ、日常をそよぐのみ。いつものように学校で掃除をし、生徒の面倒を見る。気分転換に幼なじみと会ってクダを巻く。それだけ。
描写としても驚くほどシンプルだ。基本、歩いているか、会話しているかだけ。その意味では、実に二ノ宮隆太郎作品として演出のハッキリした映画であり、主人公のあり方も『枝葉のこと』『お嬢ちゃん』とほぼ変わらない。家族に対して感情を吐き出す場面はあっても、概ね、人と話しているときは突っ立っているだけ。なのに、である。それなのに映像から尋常ならぬ緊張感が漂う。これはなんとしたことだろう。
二ノ宮隆太郎の映画はいつもそうだ。ただ歩いているだけなのに、ただ面と向かって話しているだけなのに、そこに異様な空気が張り詰める。たいしたことも話していないのに、目が離せなくなる。なぜか。恐らく、主人公が何を考えているかわからないからだろう。何を言い出すか、何をしでかすかわからない。予断を許さない。だから、なんでもない描写がなんでもなくなる。意味と意志を重く投げかけてくる。
過去に『枝葉のこと』『お嬢ちゃん』が発表されたとき、北野武映画との類似を叫ぶ声が多く聞かれた。「歩いているだけ」の描写に加え、主人公がずっと仏頂面で余計なことを話さないからだ。とりわけ『枝葉のこと』では二ノ宮自身が北野武ばりに主役を張って、同様の仕草を見せるのだから致し方ない。しかし、もはやそんな「背比べ」などどうでもよくなっている。二ノ宮作品はもはや有名映画作家の模造品ではなく、独自の立ち位置、歩み方を獲得しつつある。それが今回、映像の面からも明確になった。
瀬々敬久が指摘するように、前2作で見られたような手持ちカメラ&ワンシーンワンカットの撮影を、二ノ宮は今回、捨てている。基本的にフィックス(カメラを台座に固定した撮影)であり、会話場面では切り返しも多用している。大きく変わった。それなのに、以前と同様の緊迫感がみなぎっている。いや、より成熟した迫力を獲得したというべきだろうか。いよいよ、場面がどこへ飛んでいくかわからない。暴発寸前の空気がビシバシ飛んでくる。すごい。本当にすごい。すごいとしか言えない。
当然、凡百のお涙頂戴の「難病もの」になっていない。登場人物に同情を寄せつけず、憐憫(れんびん)も請わない。そこにある、ありのままの現実だけを突きつける。実に厳しい。その厳しさが凜とした空間を維持させる。フィクション=ウソの空間を本物にする。結果、「人間」が浮かび上がる。人間が織りなす日々の悲喜こもごもが映像からにじみ出す。それが筆舌に尽くしがたい感動、味わいとなる。
幕間(まくあい)の愉悦も忘れていない。光石に当て書きされた主人公と松重豊演じる親友、その両者の一連の場面には楽屋落ちを超えた弾みがあり、まさに眼福。「ちゃーしい」(「うるせえ」という意の博多弁)と互いに叫んで笑い合う姿は文字どおり、気の置けない同県人。「張り詰めた現実」がみなぎる劇中にあって、息継ぎのための「ユルイ現実」とするべきか。すっかりオッサンと化した風体で登場する松重を見るだけでも一見の価値がある。これほど野暮全開の松重も珍しい。思わず吹き出す。これも、いい采配。
そろそろ一般観客も二ノ宮隆太郎という才能に自覚的になった方がいい。ここには映画の可能性がある。この作家そのものが「映画の可能性」である。新たな地平へと続く「映画のとびら」である。
題名に関しては意図が読めない。そのあたりも二ノ宮作品らしいといえばらしいだろうか。もしかしたら、二ノ宮から観客それぞれに投げかけられた課題かもしれない。ここにも開くべき「とびら」がある。
どんな映画にも「とびら」はある。それぞれの「とびら」を通して才能や感動にもっともっとふれていただきたい。新しい才能を発見する喜びも、映画を見る醍醐味のひとつなのだから。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。
いつも「映画のとびら」の連載をご愛顧いただきありがとうございます。
急なお知らせとなりますが、この248回をもちまして「映画のとびら」の連載企画を終了とさせていただきます。
楽しみにされていた読者の皆さまには誠に申し訳ございません。
これにて「映画のとびら」は終了しますが、今後もさまざまな映画を楽しんでいただき、皆さまにとっての大切な一本に出会えることを願っております。
4年間の長きにわたるご愛顧に感謝申しあげます。
本当にありがとうございました。
OPカード編集担当