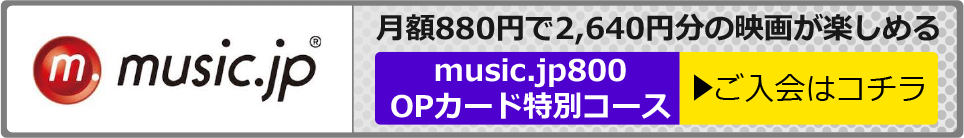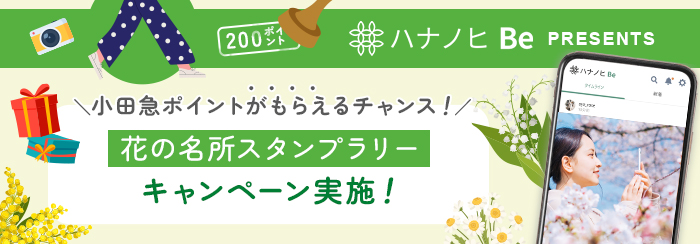特集・コラム
映画のとびら
2022年7月29日
きっと地上には満天の星|映画のとびら #194

 © 2020 Topside Productions, LLC.All Rights Reserved.
© 2020 Topside Productions, LLC.All Rights Reserved.ニューヨークに暮らすホームレスは6~7万人を数えるという。うち、年少者の数は約2万2千人。その現実に触発され、地下空間に住むホームレス母子の姿をフィクションとして描いた感動の人間ドラマ。
マンハッタンの地下トンネルに潜入するなど、10年近くも独自に取材を重ね、脚本と監督を兼任し、さらに自ら母親役を演じたのは、これが長編監督デビュー作となるセリーヌ・ヘルド。彼女とともに監督を務め、脚本と編集を兼任したのは、ヘルドとニューヨーク大学在学中に知り合ったというローガン・ジョージ。ホームレスの少女役には、これが映画デビューとなるザイラ・ファーマー。2020年9月に開催された第77回ヴェネチア国際映画祭の「国際批評家週間」に出品され、マリオ・セランドレイアワード最優秀技術貢献賞を受賞。2022年3月25日に、晴れてアメリカで劇場公開されている。
母子が暮らす地下空間とは、ニューヨークの地下に位置する廃トンネルのこと。そこで育った5歳の少女リトル(ザイラ・ファーマー)はまだ地上に出たことがない。翼が生えたら、上に出られると思っている。地上からこぼれるわずかな光の中、地下空間に舞いあがるほこりのきらめきを、夜空の星のように空想していた。母親のニッキー(セリーヌ・ヘルド)は、そんなリトルを置いて地上と地下を行き来している。
最初の30分は観客にとって一種の試練だろう。地下空間の狭く、閉じられた視界、その闇の中を写す映像は重苦しく、見る側の心さえ押しつぶすようだ。カメラはほぼ手持ち。不安定かつ狭い視野。どうしたって気持ちが苛立つ。しかし、やがて自治体の職員が再開発の名目で彼らの「聖域」へと乗り込んでくるや、事態は一変。ホームレス母子は地上への「避難」を余儀なくされる。そして、そこから映像が弾み出す。物語に新鮮なベクトルがはっきりと明示されていく。
なぜ母子は地下に暮らしていたのか。母親は日々、地上へ出て何をしていたのか。それらを示す「説明」も「回想」も、この作品は採用しない。あくまでカメラは母子に寄り添い、そこからにじむ情報だけを現在進行形で観客に提供する。徐々に見えてくる母親の「日常」とともに、映画は残り1時間、母子の逃避行をどんどん加速させ、その「運動性」の中に観客を巻き込んでいく。
クライマックスは、言ってしまえば『となりのトトロ』(1988)で描かれる姉妹の危機と状況は変わらない。母の必死の疾走と叫び、それが映画的というほかないスリルを形成し、やがて意外な「決断」へとたどりつく。この母の行動は驚きとともに、見る者の感動を否応なく駆り立てるだろう。その哀しみとも温もりとも判然としない奇妙な感慨は、ついには我々への「問いかけ」にすら変容するのではないか。
都会のホームレスという社会事情は、もちろんこの作品の看板要素である。しかし、そういった問題意識の果てに、ひと組の母子をめぐる確かな情感を最小単位で描ききったこと、それを短い時間と事件の中に躍動感をもって刻んだこと。その構成力と演出力にこそ最大の敬意を払わなければいけないのではないか。
監督と脚本をこなしたこの男女ユニットは、決して大きくない製作費の中、配慮に富んだ工夫と映像処理を見せた。優れたデビュー作といっていい。彼らの才能は満天の星のようにきらめいている。中には満点の声を上げる者もいるだろう。「地上」へ這い上がってきた彼らがどんな翼を持ち、どこへ飛んでいくのか。我々観客は、空を見上げながら、その行方を追っていかなければならない。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。