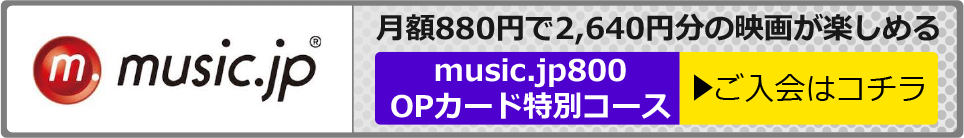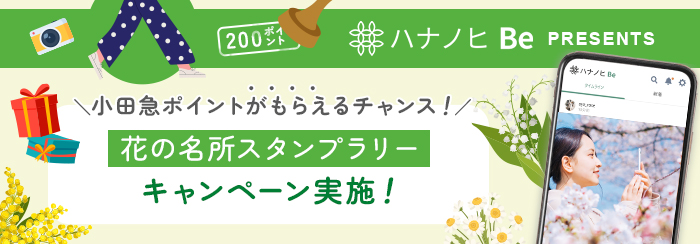特集・コラム
映画のとびら
2022年11月10日
ある男|映画のとびら #217

 ©2022「ある男」製作委員会
©2022「ある男」製作委員会作家・平野啓一郎が2018年に発表し、読売文学賞を受賞した同名小説を映画化。かつてのクライアントである未亡人から亡き夫の身元調査を依頼された弁護士がたどる意外な真実への道のりを描く。監督は『愚行録』(2017)、『蜜蜂と遠雷』(2019)の石川慶。
宮崎に住む里枝(安藤サクラ)は離婚の末、息子を連れて故郷の宮崎へ戻り、実家が営む文房具店のレジに立っていた。そこへ現れたのが、林業の職に就く男・谷口大祐(窪田正孝)だった。仲を深めたふたりは結婚し、女児にも恵まれる。しかし、家庭を持ってから3年後、大祐は山の作業場で倒木の下敷きとなって圧死してしまう。大祐は彼の親族とずっと疎遠だった。とはいえ、さすがに訃報を届けざるを得なかった里枝は、群馬の伊香保から大祐の兄・恭一(眞島秀和)を呼ぶことにするのだが、恭一は大祐の遺影を見るなり、驚くべきことを言い出す。「これ、大祐じゃないです」と。混乱した里枝はかつて離婚調停で世話になった弁護士・城戸章良(妻夫木聡)に連絡をとり、夫の身元調査を頼むことにする。その結果、大祐と名乗っていた里枝の夫は、名前もはっきりとしない全く別の男性であることが判明したのだった。
仲睦まじい再婚カップルの人間ドラマから始まる物語は、やがて妻夫木聡演じる弁護士を一種の探偵役として、一気にミステリーの色合いを強めていく。谷口大祐と名乗っていたミスターX=「ある男」とはいったい誰なのか。本当の谷口大祐はどこにいるのか。弁護士の城戸がたどり着くミスターXの正体と過去、本当の谷口大祐をめぐる人間模様が解明されるプロセスが、この作品の醍醐味のすべてといっていい。事件の解明とともに、弁護士自らが苦い現実と真向かい、思わぬ落とし穴にハマっていくあたり、レイモンド・チャンドラーやダシール・ハメット、ロス・マクドナルドらの探偵小説を思わせる気分も味わえようか。観客によってはもっと心の深淵をのぞき見るかのようなエンディングが待っている。
他人の人生が取って代わられるからくり自体はさほど驚くものではない。それよりも観客の感情を強く揺さぶるのは、ミスターXが谷口大祐の名前を手にするまでの過去描写だろう。窪田正孝によってリードされる回想場面の数々は、そんな道を歩むことになったひとりの男の悲劇である。その部分の語り口は鮮やかで、どんなに無関心で接していても、いつの間にか映画に引き込まれていくはずだ。
妻夫木、安藤、窪田の主要3人以外では、事件の秘密を知っていると思われる囚人役の柄本明が異彩を放つ。役割的には作家トマス・ハリスが生んだ魅惑の犯罪者・ハンニバル・レクターと同じで、さしずめ妻夫木はウィル・グレアム、あるいはクラリス・スターリングといったところ。といっても『羊たちの沈黙』(1991)や『レッド・ドラゴン』(2002)のような凄惨な殺人劇が展開されるわけではない。柄本自身、飄々と役を演じており、事件をいたずらっぽくかき回してほどよくイライラさせてくれる。
ミスターX、本物の谷口大祐をめぐる関連人物に仲野太賀、清野菜名、河井優実、でんでん、きたろうらが登板し、弁護士の妻には真木よう子、弁護士の同僚に小籔千豊と、脇の脇まで出演者は豪華な布陣。石川慶という監督への評価の高さが伺える。それぞれの芝居を見ているだけでも楽しいだろう。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。