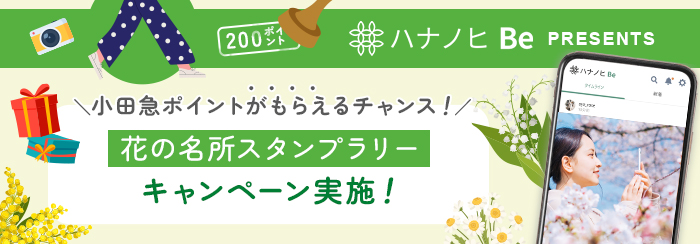特集・コラム
映画のとびら
2023年2月16日
ちひろさん|映画のとびら #236

 ©2023 Asmik Ace, Inc. ©安田弘之(秋田書店)2014
©2023 Asmik Ace, Inc. ©安田弘之(秋田書店)2014『ショムニ』(1995-1997)で知られる漫画家・安田弘之が2013年に発表した同名コミックを映画化。海辺の町の弁当屋で働く元風俗嬢のマイペースな日常を淡々と、でも確かな情感の中に描いていく。タイトルロールに有村架純。監督は『愛がなんだ』(2019)、『窓辺にて』(2022)の今泉力哉。有村と今泉はテレビドラマ『有村架純の撮休』(2020)に次ぐ顔合わせとなる。
ひとりの髪の長い女性が、公園で猫とたわむれ、ブランコをこぎ、漁港を散策している。彼女、ちひろさん(有村架純)は「のこのこ弁当」で働いている元風俗嬢。彼女の過去を知っている男性客が現れても笑顔で対応、店の同僚(根岸季衣)に「オトコのあしらいがうまいね」と冗談を飛ばされても涼しい顔。どんな人にも変わらぬ距離と態度で接する、ちょっとフシギな女性。今日も、悪ガキにいじめられているホームレス(鈴木慶一)を助け、アパートで体まで洗ってあげたりしている。そんな彼女が気になって仕方がないのか、女子高生のオカジ(豊嶋花)はちひろさんを目にするたびにこっそりとスマホで盗撮。でも、ちひろさんはオカジの行動を知っていた。それどころか、両親とうまくいっていない彼女の苦悩まで見抜く。やがてオカジだけでなく、母子家庭の孤独な小学生(嶋田鉄太)、オカジの同級生で不登校のベッチン(長澤樹)、威圧的な父と断絶中の青年(若葉竜也)といった面々が、ちひろさんに心を開いていくのだった。
沸騰することなく、冷めることもなく。でも、ぬるま湯というわけでもなく。今泉映画における「人肌の心地よさ」を感じている向きには、例によって居心地のよい時間が続く作品。ただし、恋愛映画ではない。恋愛を含めた人生の「酸いも甘いも」をひと通り体験し、その先へ一歩、歩み始めた人間の物語、というべきだろうか。その名も「ちひろさん」という名を掲げた女性は、だからどこか達観したところのある人に映るかもしれない。その周りに「悩める人々」が集まってくる。そこから生まれるささやかなドラマ。
基本、ちひろさんは受け身。ちょっとお節介も焼くけど、慈善家でも菩薩様でもない。でも、厭世家、人嫌いというわけでも、どうやらない。来る者は拒まない。結果、彼女が天使に見える人が出てくる。彼女を慕う人も増えていく。その静かな情緒が温もりを生む。それが人肌の気分となる。
基本、ちひろさんは変化しない。そのまんま。でも、物語を通して、ゆっくりと、ほんの少しだけ心が変わる。フレームインでサラリと画面に現れた彼女は、サラリと外に出て行く。そんなちひろさんの人生のひとつの「通過点」を描いた作品ともいっていい。いわば、これは彼女の「お弁当屋時代」編。
基本、ちひろさんという人物のスケッチである。劇映画だけど、架空の人物を見つめた記録映画という表現もアリかも。風のような人、風のような映画。観客はその風を頬に受けながら、なんでもない時間の変化を感じていく。徐々に、何かが満ちてくる。映画が終わる頃、そこにはどんな感情が待っているのか。
有村架純は、どこかとらえどころのない主人公を、いい空気感、いい重さの中で表現している。得体が知れない感触は、もしかしたら本人に通じるところが大なのかもしれない。無論、ちひろさん=有村架純ということではない。ただ、主人公が背負ってきた過去とその結果の現在は、有村架純の持っている雰囲気とそんなに距離が遠いとも思えない。思えば、有村架純もまた映画という町、映画という弁当屋を移り暮らしていく人なのだから。そんなことを考えさせるのも、この映画ならではの感触。
有村架純の女性的ななまめかしさ、人間的生々しさを見るなら廣木隆一作品に限るが、今泉映画はその一歩手前の有村架純の「心の真実」を描いているといっていいかもしれない。それを見る喜びもここにはある。両者の最初の顔合わせ作品『有村架純の撮休』の延長にある作品として接しても悪くない。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。