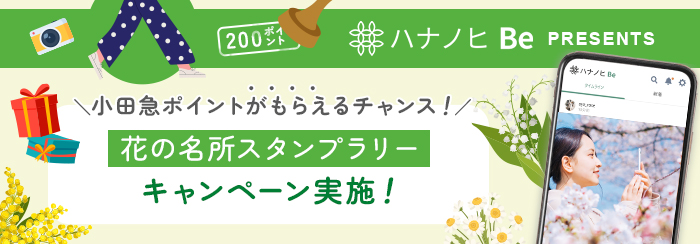特集・コラム
映画のとびら
2023年2月22日
フェイブルマンズ|映画のとびら #237

 © Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
© Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.第80回ゴールデングローブ賞の「ドラマ部門」で作品賞、監督賞(スティーヴン・スピルバーグ)を受賞し、第95回アカデミー賞でも作品賞、監督賞、主演女優賞(ミシェル・ウィリアムズ)、助演男優賞(ジャド・ハーシュ)、脚本賞(スティーヴン・スピルバーグ、トニー・クシュナー)、美術賞(リック・カーター、カレン・オハラ)、作曲賞(ジョン・ウィリアムズ)の6部門で候補となっている人間ドラマ。スピルバーグの少年期の記憶を下敷きに、映画に心を奪われた少年が家族とのふれあいの中で、やがて映画業界へと歩み出すまでを優しく感動的に描いていく。題名の「フェイブルマンズ」とは、スピルバーグ自身を投影した主人公サミー・フェイブルマンの一家「フェイブルマン家」を指したもの。
1952年1月10日。その日は6歳のサミー(マテオ・ゾーリャン)にとって人生で初めて映画館で映画を見た記念日となった。両親(ポール・ダノ&ミシェル・ウィリアムズ)に連れられて見たその作品はセシル・B・デミル監督、チャールトン・ヘストン主演の『地上最大のショウ』(1952)。その後、列車と乗用車の衝突場面をおもちゃの列車で何度も再現しようとするサミーを見た父親は、彼に8ミリカメラを買い与えたが、これがサミーの映画好きにさらに拍車をかけた。初期の「サミー作品」の役者はサミーの妹たち。やがて父の転勤に伴い、ニュージャージー州からアリゾナ州へと引っ越すと、少年サミー(ガブリエル・ラベル)はジョン・フォード監督の『リバティ・バランスを射った男』(1962)の影響から大がかりな西部劇や戦争映画を学校の級友たちと撮り始める。そんなある日、一家でキャンプに出かけたサミーは、何気なく向けたカメラのファインダーの向こうに思いもしない光景を撮ってしまうのだった。
スピルバーグの映画、またはスピルバーグ自身に関心がある向きには、いつまでも、いくらでも楽しむことができる作品だろう。彼の映画への目覚め、影響された映画、工夫に工夫を重ねる自主映画作り、出会った人々……、そのどれもにスピルバーグ作品の要素を重ねては勝手に興奮し、得心できる。それぞれの心にあるスピルバーグ像をいかようにも自己流に分析、解体できる場所がスピルバーグ自身から与えられるなんて、なんと楽しいことか。映画ファンにはたまらない「スピルバーグ・ネバーランド」としていい。
一方で、スピルバーグに関心がない観客にはどうかといえば、そこそこ骨のある人間ドラマにも仕上がっているので安心されたい。スピルバーグはコンピューターに詳しい理系タイプの父がいて、ピアノで心の声を歌にする情感豊かな母がいた。そこに3人の妹と、父の親友(セス・ローゲン)も加わり、温もり豊かな家庭が築かれている。ただし、それは幸せな情景の一断面でしかなかった。スピルバーグの家庭事情を知る映画ファンはともかく、大半の観客は一家がたどる運命に人生の悲哀を見るだろう。
映画と戯れる少年も決して順風満帆な思春期を送ったわけではなかった。後に『シンドラーのリスト』(1993)という名作を撮るスピルバーグは、文字どおり、ユダヤ人一家の生まれである。ハリウッドという映画の都はユダヤ人の占める割合が多い場所だが、少年時代のスピルバーグはその出自にコンプレックスを抱く環境にも置かれていたのだった。一種のマイノリティーの物語としてもこの『フェイブルマンズ』は「苦み」を抱えた渋い人間ドラマに仕上がっており、その点でも興味は尽きないはずだ。
自伝というより、本人による評伝と解釈した方がいいかもしれない。実際、描かれる出来事がどこまで事実なのか、誰にもわからないのだから。同時に、題名が示すとおり、これは家族の物語でもある。スピルバーグにとっては「一家の記憶」を感情レベルで再現した作品といってもいいだろう。また、それらを踏まえた上での「1950-60年代を背景にしたユダヤ人一家の寓話」とも換言できる。幸せばかりの家庭なんてなかなかない。問題のない家庭だって多い。スピルバーグの一家も同様だった。楽しいこともあれば苦しいこともある。それが人生。つまるところ、この映画は生きること、生きてきたことへの讃歌なのかもしれない。スピルバーグ映画を見る楽しさ、喜びは、人生をそこに知ることと見つけたり。それでなくとも、もはや人食い鮫も異星人も、冒険的考古学者も遺伝子改良恐竜も、我々の人生の一部なのである。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。