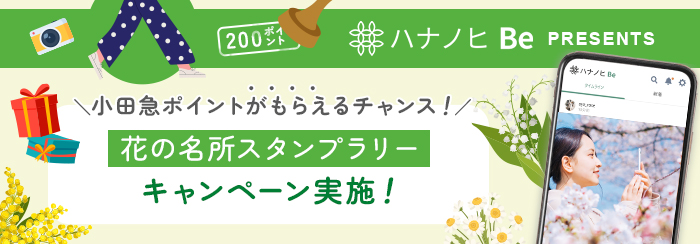特集・コラム
映画のとびら
2023年3月10日
トリとロキタ|映画のとびら #242

 ©LES FILMS DU FLEUVE – ARCHIPEL 35 – SAVAGE FILM – FRANCE 2 CINÉMA – VOO et Be tv – PROXIMUS – RTBF(Télévision belge)
©LES FILMS DU FLEUVE – ARCHIPEL 35 – SAVAGE FILM – FRANCE 2 CINÉMA – VOO et Be tv – PROXIMUS – RTBF(Télévision belge)Photos ©Christine Plenus
長編第3作『イゴールの約束』(1996)で初めて日本に紹介されて以来、一本たりとて否定的な見解を集めないダルデンヌ兄弟、渾身の一作。アフリカからベルギーへと渡ってきた疑似姉弟の過酷な生活を容赦のない現実感の中に刻んでいく。「姉弟」を演じるのは、両者ともこれが映画初出演となるジョエリー・ムブンドゥとパブロ・シルズ。2022年開催のカンヌ映画祭では「75周年記念大賞」を受賞している。
現代のベルギー、リエージュ。ひと組の姉弟がイタリア料理店で客向けのカラオケ歌唱をしている。十代後半の姉はロキタ(ジョエリー・ムブンドゥ)、小学生と変わらぬ年齢の弟はトリ(パブロ・シルズ)。だが、本当の姉と弟ではない。ロキタはカメルーンから、トリはペナンからベルギーへと亡命をはかる途中で出会い、固い信頼関係で結ばれたのだった。ベルギーでは生活のため、ビザを取得するため、互いを姉弟と偽ってギリギリの暮らしを続けているふたりだったが、祖国への仕送りだけでなく、密航を仲介した業者から稼ぎを巻き上げられるなど、イタリア料理店での歌だけでは暮らしていけない。裏ではシェフのベティム(アウバン・ウカイ)の指示のもと、麻薬の売人として夜の町を動いていた。このままでは何も変わらない。焦ったロキタは偽造ビザ取得を条件に、ベティムからさらに危険な仕事を請け負うのだった。
役者に演技経験なし、劇音楽なし。ダルデンヌ兄弟の方法は例によって変わらず、それ自体に新味はない。そこからあぶり出されるのは当然、むき出しの現実で、移民たちの苦しい日々が眼前に突きつけられる。ダルデンヌ兄弟の作品を一本でも知る観客には、予想されるとおりの展開といっていい。すなわち、安定した仕上がりの作品なのだが、物語が終局を迎える頃、冷静のままでいられる者は皆無だろう。
感情の高まりがこれまでになく大きい。尋常ならざるかたまりとなって迫ってくる。ダルデンヌ兄弟の作品を見慣れた人間にとっては恐らく多分に新鮮な感触であり、驚きを持って迎えられるのではないか。感情をただ丸裸にしているだけではない。どこか幾層にも重なった複雑な情感がそこに生まれているからだ。
情感の真相は姉弟の描き方に隠されている。彼らの疑似家族状態は生活を営むための利害関係の上に成り立っているものだが、実はそれ以上に心の交感があった。姉は弟の声を日に一度は聞かないと耐えられない。弟も姉と長くは離れていられない。その設定はロキタが「危険な仕事」を請け負うことで観客に明らかになるわけだが、その叫びが耳に届くとき、この姉弟のすさまじいばかりの友情、いやそれを超えた一心同体的な結びつきを知る。あまりに痛々しい。あまりに生々しい。そして、美しい。
一種の共依存ともいえるだろうか。男女の枠を超えた愛情だと表現する向きもあるかもしれない。そのどちらをも満たすものとなれば、それはつまり家族だろう。この姉弟は疑似を超えた家族関係に進んでいた。いや、疑似ゆえにいよいよ本物以上の家族になったというべきか。
あまりに純真なこの姉妹の姿はダルデンヌ兄弟とて当初の計算を超えるものになったのではないか。無論、トリとロキタ、それぞれを演じた役者による部分も大きいのだろう。ほぼ初の演技に近い彼らが見せるそれは、そのまま姉弟の無垢につながった。想定を超えた化学反応がそこに巻き起こった。ダルデンヌ兄弟の作品にふれたことのない観客には衝撃の事態に映るのではないか。もはや映画どころではない。現実感を超えた現実。ナマの人間の苦しみ、喜び、哀しみがきっと真っ直ぐに、新鮮に飛び込んでくる。しかも最高の「家族」の物語に接して。そんな「僥倖」に嫉妬を覚える映画ファンもいるかもしれない。
なんという切ないラストだろう。同時に、なんと大きな温もりを感じさせる後味だろう。うかつに涙を流すことも許されない。不用意に「リアル」「感動」などという単語も持ち出せない。気高い充実がただまぶしい。同様の不法移民を扱った『イゴールの約束』などにはなかった気分がここにある。鋭利な現実直視の姿勢の中に社会と人間を掘り下げ続けた真摯な兄弟映画監督ならではの至芸であった。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。