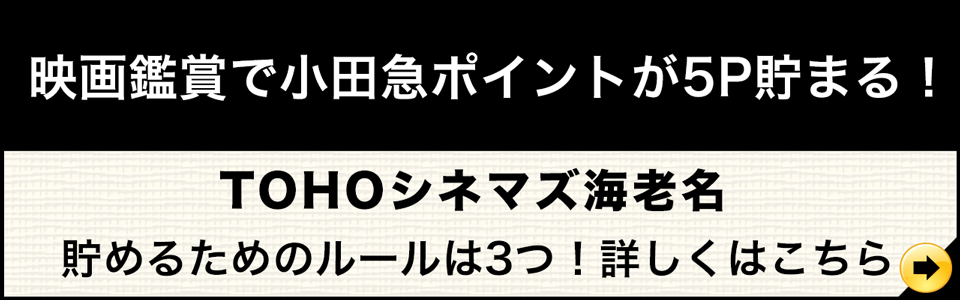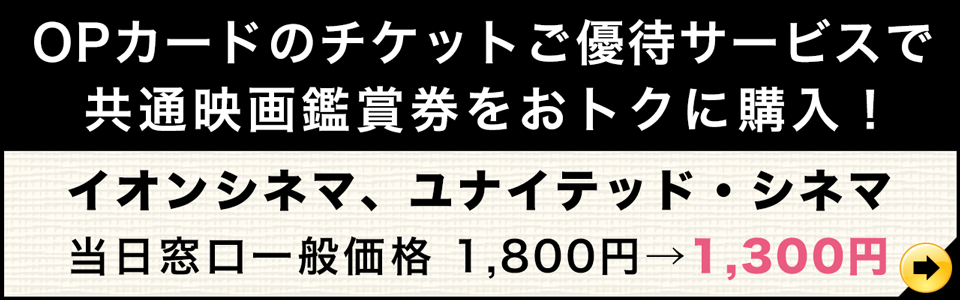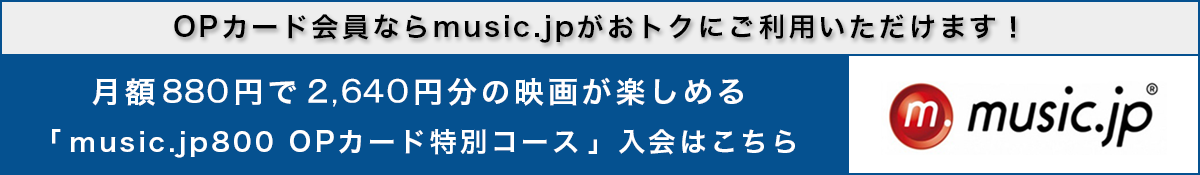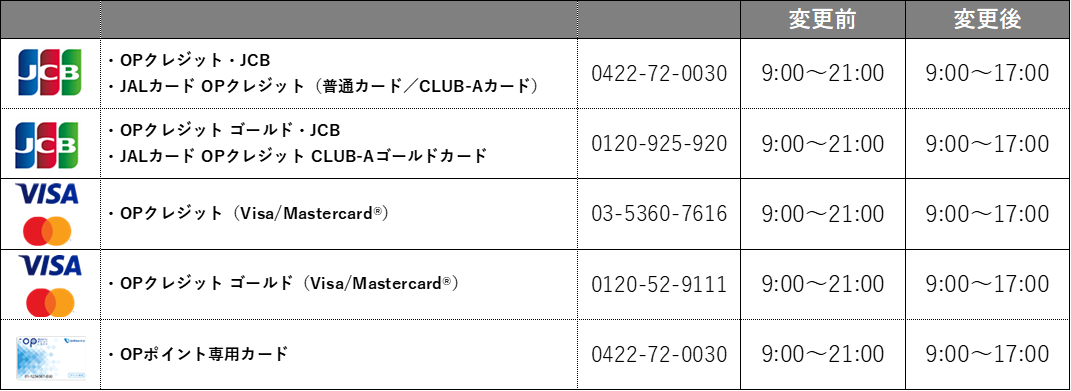特集・コラム
映画のとびら
2019年4月12日
マローボーン家の掟|新作映画情報「映画のとびら」#002【監督インタビューあり】

マローボーン家の掟
2019年4月12日公開
 ©2017 MARROWBONE,SLU; TELECINCO CINEMA,SAU; RUIDOS EN EL ATICO,AIE. All rights reserved.
©2017 MARROWBONE,SLU; TELECINCO CINEMA,SAU; RUIDOS EN EL ATICO,AIE. All rights reserved.注目作が続く現代スペイン映画界から、またひとつ心を打つ佳作が到着した。
舞台は1960年代末のアメリカはメイン州。母ローズ(ニコラ・ハリソン)に連れられて、マローボーン家の4人兄弟が越してくるところから物語は始まる。美しい森の中に建つその館は、かつて母が生まれ育った家。イギリスで忌まわしい事件に遭遇していた彼らにとって、誰も自分たちのことを知らない地での再出発こそ人生をやり直す唯一の手段であった。しかし、まもなく母は病死。長男ジャック(ジョージ・マッケイ)に一家の未来が託されたとき、さらなる災厄がイギリスから訪れ、一発の銃声を響かせるのであった。
邦題に掲げられた「掟」とは、母の遺言、および兄弟の中で交わされた約束事のこと。明文化するなら「成人になるまでは屋敷を離れてはならない」「鏡を覗いてはならない」「屋根裏部屋に近づいてはならない」「血で汚された箱に触れてはならない」「“何か”に見つかったら砦に避難しなくてはならない」という五つ。これらにどのような意味が隠され、明らかにされていくのか。そのプロセスが物語に緊張を与え、情感の山場を築いていく。
この映画をホラーと呼ぶのはたやすい。実際、恐怖映画の常套手段ともいえるショック演出が随所にひしめいている。しかし同時に、そう単純にカテゴライズするのがためらわれるような美しさがこの映画にはあった。それは懸命に日々を送る兄弟たちの姿であり、長男によってつむがれた彼ら自身の秘密である。
屋敷に閉じ込められた子どもたちを描くという点で、V・C・アンドリュース原作の『屋根裏部屋の花たち』(1987)を連想する向きもあるだろう。あるいは、見えざるものを可視化する仕掛けに同じスペインの代表的作家アレハンドロ・アメナーバルの『アザーズ』(2001)を思い返す観客もいるかもしれない。「恐ろしゅうて、やがて哀しき」という語り口に『シックス・センス』(1999)の気分を感じる者もいるだろう。しかし、この映画で長編監督デビューしたセルヒオ・G・サンチェスはトリックや絶望の涙に逃げようとしない。ミステリーの味付けに甘えたりもしない。そして、痛々しい残酷描写を正面から突きつけるような野暮もしない。一個の少年の一途な想いと尽力を、時に娯楽性豊かに、時にスリラーの形を借りて回収しているだけである。決してすべてが斬新というわけではない。しかし、代わりに堅実な映画的記憶の積み上げがある。その意味では、これは精緻に構成されたファンタジーであり、思春期の無垢を的確に刻んだ人間ドラマだとしていい。
謎解きの結果に肩を落とす観客もいるかもしれない。イギリスからの脅威をめぐる真相に「そんなバカな」と無理を叫ぶ声も出るかもしれない。それでも、胸の痛くなるような悟りが刻まれるラストの情景には誰もが心を洗われるのではないか。ファンタジーの雰囲気を借りた厳粛な「罪と罰の物語」として、この決着を受け取るのも一興だろう。
――この映画には、さまざまなジャンルの要素が豊かにあふれています。謎めいたファンタジーであり、先の読めないミステリーであり、固い絆の家族を描いた人間ドラマであり、最終的には胸が熱くなるラブストーリーであります。あらゆる映画の面白さを凝縮したかのような濃厚な仕掛けは、監督デビュー作としてのあなたの意気込みが反映された結果なのでしょうか。
サンチェス:その通りだと思う。長編映画を撮りたいという思いが強かったので、いろいろなジャンルをひとつの作品の中に取り込もうとしたんだね。最も描きたかったのは、トラウマによって壊れた人間の姿だ。鏡が割れると、いくつもの断片ができるように、ひとつの人格には家族や心の傷、ロマンティックな気分といった数々の断片がある。僕にとっていちばん難しかったのは、その断片を物語の中でうまくつなぎ合わせることだった。

――脚本作りは困難を極めましたか。何稿ほどリライトを重ねたのですか。また、それはどれほどの日数、時間を要したのでしょうか。
サンチェス:最初は早かったんだ。遊びのような形でプロデューサーのベレン・アティエンサに「こんなことを考えているんだけど」ってプロットみたいなのを送ったら、「これは面白い。すぐに脚本を書いてくれ。一日に3枚のペースでもいいから」と言われてね。で、本当に一日3枚のペースでプロデューサーに送ったんだ(笑)。まるで小説を書くような気分だったな。プロデューサーからのフィードバックをもらいながら、第1稿を書き上げたのは3週間くらいたった頃だった。ただ、そこから撮影台本にまとめるまでが大変で、結局、24稿も重ねることになったんだけどね。
――アメリカを舞台に設定した理由を教えてください。また、その撮影場所にあなたの故郷アストゥリアスを選ばれたことに、どんな利点がありましたか。
サンチェス:当初はスペインを舞台にする予定だったんだけど、これを英語で撮るのかスペイン語で撮るのか、脚本を読んだ関係者が尋ねてきたんだ。やっぱり、英語で撮った方が資金調達にしても何にしても広がりが出るのは当然だったし、実際「英語で撮るなら資金を出してもいい」という会社もあったので、それが英語を言語にした直接の理由だね。アメリカを舞台にしたのも、その流れでのことだったんだ。主人公たちをイギリスから転居してくる人間として描いたのは、物語の設定上、できるだけ遠くから越してくる人間にしたかったから。あと、エドガー・アラン・ポーの怪奇小説が好きだったし、自分が15歳から20歳までアメリカに住んでいたことも大きい。60年代のアメリカをアストゥリアスで撮るという挑戦もしてみたかったしね。もっとも、アストゥリアスで撮ることになった背景には、アメリカに60年代を再現できるような場所がなかったこともある。子どもたちが暮らす森の中の一軒家もイメージどおりの場所が見つからなかった。物語のほとんどが、あの家の周りで起こっているというのに。だから、アストゥリアスだからこそ実現できた部分は多いんだ。長男のジャック(ジョージ・マッケイ)が自転車で向かう街にしても、アストゥリアスだからこそ自分たちの思うように作り込むことができたといえる。今、60~70年代のアメリカを舞台にした映画を撮ろうとするとき、アメリカでロケをする作品の方が少ないんじゃないかな。
――子どもたちの描写が素晴らしいです。今回、彼らのためにそれぞれ特定の楽器の音色を割り当てて音楽を構成されたそうですね。
サンチェス:音楽担当のフェルナンド・ベラスケスと相談して、物語のための音楽的文法を創作することにしたんだ。ジャックにはフルート、長女のジェーン(ミア・ゴス)にはハープ、次男のビリー(チャーリ-・ヒートン)には民族調のヴァイオリン、無垢を象徴する末っ子のサム(マシュー・スタッグ)と優しい隣人のアリー(アニャ・テイラー=ジョイ)にはチェレスタをという具合にね。アリーにはピアノも重ねて、彼らの脅威となるポーター(カイル・ソラー)にはジャジーなピアノとミュート・トランペットを当てた。最終的には、兄弟とアリーの音がひとつのテーマ曲となって融合するよう音楽的ゴールを設定している。だから、音楽の役割はすごく大切だったよ。
――音楽担当のフェルナンド・ベラスケスについてコメントをいただけますか。彼によると、あなたとは短編映画時代から長い付き合いがあるそうですね。作曲家としての彼の素晴らしさをどう表現されますか。また、映画における音楽の意義をどうお考えですか。
サンチェス:自分にとって、音楽は第2の物語だと思っている。最近の風潮として、音楽を目立たないようにしている映画が多いんだけど、私の立場は全く正反対だ。音楽自体が物語ってほしいと思っている。小さい頃、家にビデオがなくて、映画を見たらサントラ盤を買って聴いて、映画の内容を思い出したりしていたことを思い出すよ。クラシック音楽もすごく好きなんだけど、聴くたびにそこにどんな物語が潜んでいるのかを想像しながら聴いているしね。フェルナンドとは古い付き合いだ。彼は本当に素晴らしい。彼の書くメロディーは物語になっているんだよ。彼とはこれからも仕事をしていきたいと思っている。
――今回の監督デビュー作において、最もチャレンジングな部分はどこだったのでしょうか。同時に、製作する上で最も感動的だった局面はどこになるのでしょう。

サンチェス:みんなが僕の言うことに耳を傾けてくれるかどうか、だったね(笑)。スタッフは経験豊富な人間ばかりで、僕と俳優の子どもたちがいちばんのルーキーだったわけさ。撮影中、ベテランのスタッフと口論をやったときなど、ミア・ゴスが寄ってきて「あなたは初心者なんだから!」と、口論をやめるように僕を諫めたことがあったよ(笑)。もちろん、熟練のスタッフが細部にわたって手を尽くしてくれたことには感動している。
何より感動的だったのは、俳優の子どもたちと一緒にこの物語を編むことができたことだ。毎日毎日、自分の想像の中の人間が彼らによって実際に目の前で現れてくるわけだからね。俳優たちはとても寛容で、彼らの人生のすべてをかけて役に挑んでくれた。とても感動したね。脚本の仕事は孤独でつらいけど、監督はみんなに支えられて仕事ができるから楽しい。僕がやりたいことをできるように、周囲の介入から僕を守り、監督としての自由を確保してくれたのは(製作総指揮を務めた)J・A・バヨナだ。彼からは特に編集作業の段階で、作品がジャンル映画に偏らないようにアドバイスをもらった。僕としては「サスペンスのフェアリーテイル」にしたかったからね。
――あなた自身のこの映画に対する手応え、評価を伺いたいです。あなたの目指しているものにどこまで到達できた作品でしたか。
サンチェス:さっきも話したとおり、僕はルーキーで、まだ映画を評価できる立場にいないんだよ(笑)! 何しろ自分自身の監督デビュー作だしね。それに、まだ僕の中では映画製作の途中にいるような気分があるんだ。本来ならもっと時間を経て、観客として作品を見られるようになってから話すべきだと思うんだけど、あえて自己採点するなら10点中7点かな。まだまだ学ぶことがいっぱいあるし、まだまだ自分の中で育てないといけない部分もいっぱいあると思っている。
――スペイン映画界は好況なのでしょうか。英語圏向けの作品もたくさん製作されて、世界的な注目を集めている印象がありますけれども。ご自身のご意見を伺わせてください。
サンチェス:好況ではないと思う。確かに英語圏向けの作品も作られているんだけど、それはみんなが誘致しての結果であって、スペイン国内ではそのやり方に批判もある。観客は喜んでくれているんだけどね。今、スペインで景気がいいのは映画界ではなく、Netflixじゃないかな。Netflixはヨーロッパでの拠点をマドリードに作ったんだ。おかげで周囲の映画関係者が全員、仕事を持てている。そんなこと、今までなかった。実を言うと、僕自身もNetflixでドラマをひとつ作ったんだけどね(笑)。
――なんとかがんばって、劇場用映画を作り続けてください。
サンチェス:つぎは日本で撮りたいと思っている。日本へは絶対に戻りたいんだ。以前に行ったことがあるけど、大好きな国だからね。そのとき、フェルナンドも一緒に連れていくことができたら楽しいね。

1973年、スペインはアストゥリアス州オヴィエド生まれ。ニューヨークで映画を学ぶ。短篇映画製作を経て、ギレルモ・デル・トロ(『パンズ・ラビリンス』『シェイプ・オブ・ウォーター』)が製作総指揮をとったJ・A・バヨナ監督の長編デビュー作『永遠のこどもたち』(2007)で脚本を担当し、ゴヤ賞の脚本賞を受賞。続くバヨナの監督第2作『インポッシブル』(2012)でも脚本家として参加し、その興行的成功でさらに知名度を上げる。2017年、『マローボーン家の掟』で念願の長編映画監督デビューを飾った。

(C)2012 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
| タイトル | インポッシブル (原題:The Impossible) |
| 製作年 | 2012年 |
| 製作国 | スペイン・アメリカ |
| 上映時間 | 114分 |
| 監督 | J・A・バヨナ |
| 出演 | ナオミ・ワッツ、ユアン・マクレガー、トム・ホランド |
最近ではハリウッドに招かれ、大ヒット作『ジュラシック・ワールド 炎の王国』(2018)を放ったスペインの映画監督J・A・バヨナ(1975年生まれ)は、そもそも長編監督デビュー作『永遠のこどもたち』(2007)で出世街道を歩み始めた人。そのデビューをシナリオ面から支えたのがセルヒオ・G・サンチェスだった。続くバヨナの監督第2作『インポッシブル』(2012)でもサンチェスが脚本をまとめ、大ヒットを記録している。前者は、古い孤児院に秘められた謎を超常現象の中に描いた切ないファンタジー。後者は、休暇を楽しんでいたタイでスマトラ島沖地震の被害に遭ったヨーロッパ人家族の再会を感動的に描いた人間ドラマ。いずれも子どもたちの描写が秀逸で、『マローボーン家の掟』に通じるサンチェスの資質を考える手がかりになっている。見方によっては、『マローボーン家の掟』は『永遠のこどもたち』と『インポッシブル』の中間地点に位置する作風の作品といえるかもしれない。バヨナはサンチェスの監督デビュー作『マローボーン家の掟』の実現に際し、製作総指揮を担って後方支援に当たっている。ちなみに、これら3作品すべての音楽を担当しているのはフェルナンド・ベラスケスである。世界の注目を浴びたスペインの両作家にとって、ベラスケスは映画作りに欠かせない音楽言語なのであった。
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。
*『マローボーン家の掟』は、関東地区では「ユナイテッド・シネマ豊洲」、「ユナイテッド・シネマ浦和」でも上映されます。(2019年4月12日現在)
人気記事ランキング
最新情報