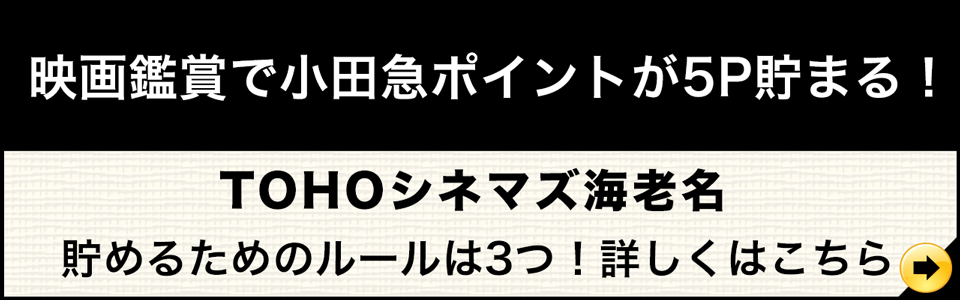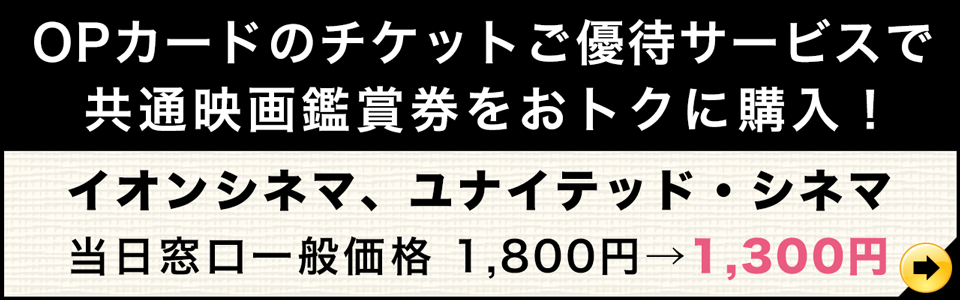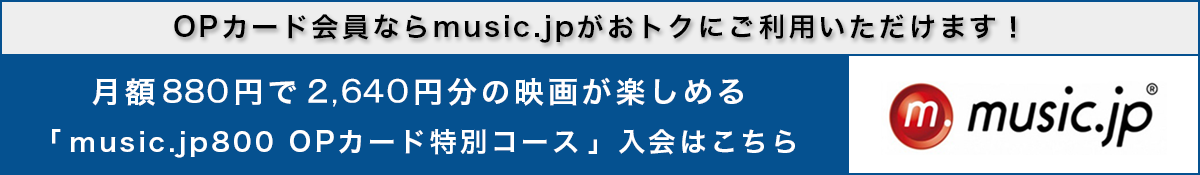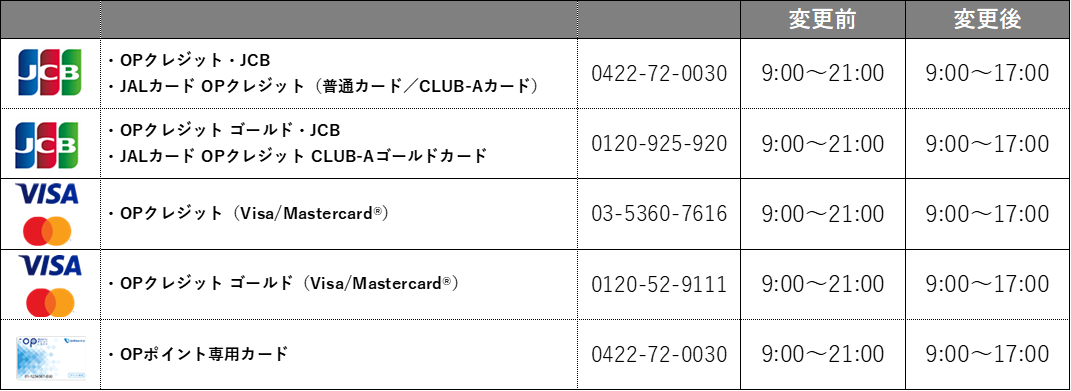特集・コラム
映画のとびら
2019年5月10日
初恋~お父さん、チビがいなくなりました|新作映画情報「映画のとびら」#007【監督インタビューあり】

初恋~お父さん、
チビがいなくなりました
2019年5月10日公開
 (C) 2019西炯子・小学館/「お父さん、チビがいなくなりました」製作委員会
(C) 2019西炯子・小学館/「お父さん、チビがいなくなりました」製作委員会結婚50年目を迎える老夫婦の心の機微を描いた物語。
頑固で笑いもしない亭主関白な夫(藤竜也)、韓国ドラマに見惚れながら飼い猫に話しかける妻(倍賞千恵子)。子どもたちが独立しているふたりには、ろくな会話もない。献身的な妻は毎日、夫のために弁当をこしらえる。その弁当を抱えた夫の時間のつぶし場所といえば、近所の将棋道場。夫の姿を道場の外から見かけて妻は手を振る。けれど、夫は知らんぷり。素っ気ない態度の夫に、妻は心が痛い。フラリとやってきた娘(市川実日子)にふと、こぼす。「お母さんね、別れようかなと思っているの、お父さんと」。そして、ある日、飼い猫のチビまで姿を消してしまう。妻の心の穴はますます広がってしまった様子。
何気ない日常と、なんてことのない事件。それを淡々と、でも、着実に積み重ねていくドラマは、まこと、必要十分な感情、出来事しか描いていない。思わせぶりな説明も、半端な感傷もほとんどない。軽妙ではあっても、大仰に笑わせようとするような気取りなどない。一見「ありふれた風景」である物語を、驚くほどのストイシズムをもって、堂々と、でも優しく平易なタッチで語りきる。この作品を前にすると、世の中に「おしゃべり」で「情感過多」な同系作品がいかに多いかと感じ入るのではないか。
まさに小林聖太郎という映画作家の感性と才気に裏打ちされたそれらは、具体的には「現実感」への対峙から生まれるものである。この人はウソの人間を描かない。ウソの涙を描かない。だから、夫婦の物語も安手のメロドラマに陥らない。本当に見せるべきは隠された真情、妻が知り得なかった心。そこへ向かって、階段をひとつひとつ上がっていった観客は、クライマックスでついに真の涙に暮れる瞬間を発見するのである。無駄と無理のない語り口から生み出される澄んだリリシズム。ある意味で、題名にすべてが語られているこの作品は、仮に隅々まで物語を知っていたとしても、感動が薄れることはないのではないか。
妻の有喜子を演じる倍賞千恵子は、仕草の端々が可愛く魅力的。その倍賞と私生活で長い近所付き合いがある藤竜也は、女性に優しい素顔をあえて封印しての昭和の夫・勝役。有喜子とはかつての職場の同僚にして、夫婦の間に波紋を呼ぶ志津子役・星由里子はこれが惜しまれての遺作。シニア層には同じ目線の日常譚として、若い観客には夫婦の純情に胸が打たれる愛の物語として、ちょっとふれておきたい佳作だ。
公式サイトはこちら
――お手元に企画が届いたのはいつ頃のことでしょうか。
小林:2017年の夏頃だったと思います。7~8月頃ですね。暑い日に自転車で(企画・配給の映画会社)クロックワークスに来たのを覚えています(笑)。撮影は2018年の2~3月にやりました。
――そのときには脚本は初稿など用意されていたのでしょうか。
小林:準備稿の準備稿みたいなものはありました。それをまず拝読して、その後、西(炯子)さんの漫画原作も読ませていただきました。僕としては、有喜子さん(倍賞千恵子)の孤独や寂しさ、自分の居場所のなさみたいなものがお客さんに伝われば、小さいけど可愛らしい映画になるんじゃないかな、と感じましたね。(夫婦の)キャスティング自体はもうそのとき「このふたり(倍賞千恵子と藤竜也)です!」という感じで決まっていましたから(笑)、「もう、ぜひ」という感じでした。
――監督の有喜子さんへの理解というのは、共感みたいなものだったのでしょうか。
小林:完全に自分の思いと近いというよりは、市川実日子さんが演じられた娘さんの立ち位置からの共感だったと思います。「お母さん、もっとしっかりしなさいよ」という苛立ちも含めた気持ちといいますか。「自分で決めないといけないんじゃないの!」っていう励まし、みたいな気持ちも含めて。
そういう思いを抱いている人は結構いるんじゃないですか。この映画は、そういう人たちへのお手紙にもなるんじゃないかなっていう思いもありましたね。

そういう思いを抱いている人は結構いるんじゃないですか。この映画は、そういう人たちへのお手紙にもなるんじゃないかなっていう思いもありましたね。
――脚本はどういう形で改稿されていったのでしょうか。
小林:脚本を書いてくださった本調有香さん(『人のセックスを笑うな』『blue』)は、こまやかな描写がすごく達者な方なんです。そういう枝葉末節を僕なりに取捨選択させていただいて、シンプルにしていったところはありました。直す判断基準としては、やっぱり有喜子さんの心情に寄り添っているかどうか、ですね。彼女の孤独がより浮き立つかどうか、でした。
――「シンプル」ということにつながっているかどうかわかりませんが、実に小林聖太郎作品らしいということでは、ベタベタしていない、でも乾きすぎているわけでもない、という作品の独特の感触があると思います。そこが個人的にはりりしく感じます。
小林:ご覧になる方によっては、突っ込みが足りないと感じる人もいるでしょうね(笑)。でも、ベタベタしたくないということでは、音楽のことも含めて、いつも思っていることです。「謳い上げる」ようなことはしたくない。「どう? 泣けるでしょ?」みたいなことは、ちょっと恥ずかしいんです。そちら(メロドラマ風にすること)の方が理解されやすいのかもしれませんけれど。でも、できないものはできない(笑)。
――同時に、物語の状況説明のさじ加減が難しいところでもあります。

小林:映画って気持ちが映りそうで映らないものなんですよね。そこをどうアクションとして見せるのか、どうアクションにするかということだと思います。この映画でいうなら、有喜子さんが買い物したり、料理をしたり、布団を干したりという、そういう一個一個を割としっかり撮ろうとは思っていました。皿を洗うだけにするのか、あるいはその後に拭いて乾かすところまで見せるのか。
どこまでそれを残すのか、残さないのか、とか。もちろん、一から十まで見せてしまうと退屈になってしまいますから、その一歩手前の日常のアクションの中で感じてもらえるものがあったらいいな、と思っていました。
――確かに、倍賞さんの描写には無駄と無理が感じられません。
小林:たとえば映画の冒頭で、有喜子さんの人となりや日常生活を紹介するところがありますけど、その中でキャラクターがどう見えてくるのか、ですね。それが説明っぽくなく見せられたらいいなっていうことはありました。「何にも話が始まらないじゃないか」と思う人もいらっしゃるかもしれませんけど(笑)、実はもう始まっているんです。
――そういう描写の積み重ねの結果、夫婦がお互いの「ちょっとした感情」に気づくという山場につながっていくわけですね。
小林:僕としては、倍賞さん、藤さんと(芝居に関して)大きな齟齬はなかった感じです。ホン(脚本)読みは撮影前に一回やりましたけど、そこから衣裳合わせと撮影の初日、2日目を撮っていく過程で合わせていったといいますか。ただ、勝さん(藤竜也)のお父さんの(無口で頑固な昭和男ぶり)は「これくらいかな」という程度が繊細でしたから、藤さんと一緒に試しながらつくっていったところはあります。「A、B、C、どのパターンでやりましょうか」みたいな感じで。
――表現するということでは、勝さんの方が……。
小林:難しかったと思います。やりすぎて嫌な奴に見えてしまってはいけませんし、優しすぎてもいけないし、で。そこの見せ方で「違う」と感じたときは、藤さんと話し合いました。有喜子さんに関しては、はっきりと「違う」みたいなことはなかったですね。
――かといって、有喜子さんが勝さんをリードするような見せ方でもありません。
小林:有喜子さんが主体的なアクションをとる人ではないんですよね。お話を進めていく人物ではない。受け身の人生を歩んできた人ですから。その意味では、周囲にいる娘みたいな存在がアクションの媒介になっているんですね。
――猫のチビの失踪も、夫婦の心のひだを描くための要素というわけですよね。勝さんが志津子さん(星由里子)と妻に内緒で会って食事をしているという部分も同様なのでしょう。どこを切っても、夫婦の描写が主観的すぎない。
小林:主観的な情感も描いていますけど、極端な言い方をするなら、昆虫観察的なところもあるかもしれません(笑)。夫婦のいろんな事どもを、ちょっと距離を置いて見ているんです。ちょっと冷めすぎているきらいがあるかもしれませんね、僕は(笑)。
――一方で、夫婦の出会いを描く回想シーン、あそこなどは通常なら状況説明だけに走りがちですが、それ以上にリッチな感触を見る側に与えていますね。かつての志津子さんと有喜子さんの職場での関係がわかる点でも大切な場面ですけど、気持ちの上では過去の話にしたくない、ウソにしたくないというような監督のこだわりを感じるのですが。
小林:それはありました。回想そのものはほかの映画でもやってしまう方法なんです。けど、今回だけは回想を回想として撮っていません。回想だけども、あの若いふたり(有喜子と勝)の現在進行形の物語としてあってほしかったといいますか。あそこがあるからこその、夫婦のゴールもある、みたいにしたかったところはありますね。ちょっと手を抜けば、もっと楽に撮れるところなんですけど、それでは描く意味がなかったといいますか。
――その一方で、やはり過去と地続きであるはずの勝さんと志津子さんの「密会」の説明を一切やっていません。物語上、有喜子さんはふたりの事情を知らないままになります。これまた潔いほどです。
小林:実は、何回目かの編集ラッシュまでは(カットせずに、その場面を)つけていたんです。情報としては必要かもしれませんけど、映画の流れとしては、その前後にエピソードがいくつかつながっていて、ちょっと長く感じたんですね。もし「あれ?」と思われた方がいたとしても、それを話題にして映画館を後にしていただいてもいいんじゃないのかな、と。ご覧になった方同士で「こういうことだったんじゃない?」みたいな想像していただいてもいいと思いますし、全部が全部、説明する必要もないのかな、と。僕としては、その説明の場面を切ったことに後悔はありません。このバージョンがディレクターズ・カットです。
――あらためて撮影を振り返って、倍賞さん、藤さんとのお仕事はいかがでしたか。
小林:倍賞さんは垣根のないところが非常にチャーミングな方でしたね。撮影の合間が幸せになれる現場でした。僕だけではなく、スタッフみんな、そう感じていたのではないでしょうか。人間としてそこに立っていただける。とても気持ちがいい人。声の良さもその要素のひとつです。ずっと「歌」を聴いていられるような、そんな感じなんです。撮影の最後の日に「こんな映画好きの人たちと一緒に仕事ができてうれしかった」と涙ぐまれながらおっしゃってくださって、今思い出してもグッときますね。またぜひ、お仕事をしたいなって思っています。藤さんとは助監督のときに『村の写真集』(2003)でご一緒していて、念願かなって今回、ようやく監督としてお仕事ができました。打ち上げのときに文句を言われたことを思い出します。「あのね、小林さんはね、気持ちよくOKをくれないんだよね」って。僕、OKの声が素っ気なかったみたいです。「もっと大きく“OK!”って言ってほしいんだよね、役者は」って言われました(笑)。
――小林監督ならではの、独特の可愛い映画ができあがったと思います。
小林:今まで50年秘めた想いを告白するみたいなシーンは撮ったことないですからね。藤さんの力は信じていましたけど、できるのかなって思っていました。普通、ああいうことって言わないじゃないですか。特にこのお父さんは言いそうもない(笑)。その意味では僕にとって新しい挑戦になっている作品だったのかもしれません。可愛いといえば、星由里子さんの「うふふふ」という笑い方を思い出しますね。あの「うふふふ」はなかなかできません。本当に可愛らしい方でした。

1971年、大阪府出身。大学卒業後、ジャーナリストの今井一の助手を経て、原一男監督主宰の「CINEMA塾」に第一期生として参加。その原一男をはじめ、中江裕司、行定勲、井筒和幸といった映画監督のもとで助監督経験を積み、『かぞくのひけつ』(2006)で映画監督デビュー。その他、監督作品に『毎日かあさん』(2011)、『マエストロ!』(2015)、『破門 ふたりのヤクビョーガミ』(2017)など。

(C) 2017「モリのいる場所」製作委員会
| タイトル | モリのいる場所 |
| 製作年 | 2017年 |
| 製作国 | 日本 |
| 上映時間 | 99分 |
| 監督・脚本 | 沖田修一 |
| 出演 | 山崎努、樹木希林、加瀬亮、吉村界人、光石研 |
東海テレビが制作したドキュメンタリー映画『人生フルーツ』(2016)は、固い絆で結ばれた実在の老建築家夫婦を軽やかに見つめた傑作だ。ここには、ある種の理想的な老いと生活があり、まるでフィクションのような展開も含めて、さわやかな感動に震えること間違いなし。ナレーションを担当した樹木希林もラッシュを見るなり「いいじゃない、これ」と依頼を快諾したというのも納得だ。
その『人生フルーツ』を劇映画の世界に転換させたような作品が『モリのいる場所』(2017)。こちらも実在した画家・熊谷守一とその妻を描いているのだが、妻役をこれまた樹木希林が演じている。
外国映画に目を転じるなら、『人生に乾杯!』(2007)がちょっと異色。理不尽な金銭的困窮を迎えた老夫婦が郵便局強盗に転じるというもの。老後の問題を考える意味でも見ておきたい問題作でもある。
ダイアン・キートンとモーガン・フリーマンが夫婦を演じる『ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります』(2014)は新居探しのドタバタが描かれ、『31年目の夫婦げんか』(2012)ではメリル・ストリープとトミー・リー・ジョーンズが夫婦生活を復活させようとする夫婦を演じて笑わせてくれる。
仲のいい夫婦を見せようとするとき、実際に仲のいい夫婦がキャスティングされることがしばしばある。ハリウッドきってのおしどり夫婦と呼ばれたヒューム・クローニンとジェシカ・タンディには『コクーン』(1985)、『ニューヨーク東8番街の奇跡』(1987)という素晴らしい場所が用意された。『ミスター&ミセス・ブリッジ』(1990)という作品などは、ポール・ニューマン&ジョアン・ウッドワード夫婦の実生活がにじんでこその頑固夫&良妻のドラマではなかっただろうか。
夫の本音が最後に爆発する感動作ということでは、山田太一脚本、伊豫田静弘演出のテレビドラマ『ながらえば』(1982)が必見。夫役・笠智衆の渾身の演技に涙が止まらない。
music.jp(エンタメ総合配信サイト)で関連作品をチェック!
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。
【小田急沿線での上映予定】
*川崎市アートセンターアルテリオ映像館にて上映【2019年5月11日(土)~6月7日(金)】
*『初恋~お父さん、チビがいなくなりました』は、TOHOシネマズ海老名での上映はございません。(2019年5月10日現在)
人気記事ランキング
最新情報