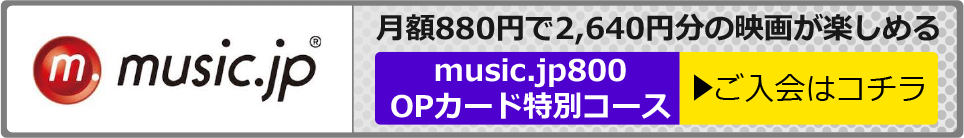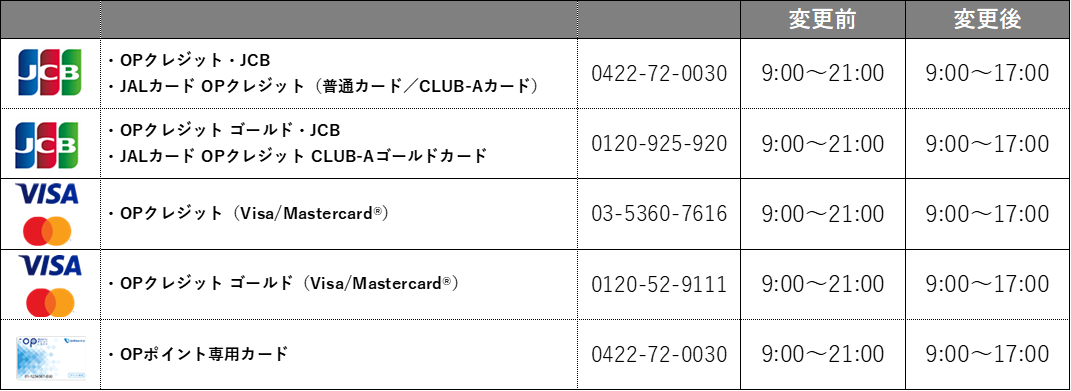特集・コラム
映画のとびら
2022年6月30日
バズ・ライトイヤー|映画のとびら #190

 (C)2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
(C)2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved.『トイ・ストーリー』(1995)に登場したアクション・フィギュア、バズ・ライトイヤーの「原点」を描くSFアクション。監督は『ファインディング・ドリー』(2016)で共同監督を務め、これが長編単独監督デビューとなるアンガス・マクレーン。マクレーンは『ニセものバズがやって来た』(2011)、『トイ・ストーリー・オブ・テラー!』(2013)という短編2作品でも監督を務めており、バズをめぐる新たな物語にとって最適の人選だったといえそうだ。
バズ・ライトイヤーは、もともと少年アンディが所有する「おもちゃ」として『トイ・ストーリー』に登場。アンディが「人生が変わるほど夢中になった映画」に登場するスペース・レンジャーをモデルに作られたものだ。では、アンディが夢中になった映画とはいったいどんな内容の作品だったのか。そんな疑問を持ったアンガス・マクレーンが開発したのが今回の作品。名前はおもちゃと同じでも、『トイ・ストーリー』の「おもちゃ」が出てくるわけではなく、続編でもない。『バズ・ライトイヤー』という「実写映画」に登場するキャラクターの物語である。いわば、新たなヒーロー映画。声の出演もティム・アレン(日本語吹き替え版では所ジョージ)からクリス・エヴァンス(鈴木亮平)に替わっている。
物語の舞台は、広大な宇宙の一角。探査のため、とある惑星に降り立ったバズがミスを犯し、結果として1200人の仲間たちが搭乗する船は破損、惑星脱出不可能の事態に陥ってしまう。船の修理のため、やむなく一時的に生活環境を整えた乗務員たちだったが、バズは地球への帰還を目指し、ハイパー航行をかなえる燃料クリスタルの生成に向け、危険なテスト飛行を惑星圏外でたびたび行っていく。
『トイ・ストーリー』の物語が「おもちゃ」ならではのかわいらしい事件や騒動に彩られていたのに対し、この『バズ・ライトイヤー』はかなり本格的なSF作品となっている。具体的には、ハイパー航行テストが生む「ウラシマ効果」、それをめぐる時間的問題がドラマの中心にあり、他作品でいえばクリストファー・ノーラン監督の名作『インターステラー』(2014)や、庵野秀明監督によるオリジナルビデオアニメーション作品『トップをねらえ!』(1988)と同じ題材、問題を扱っているといっていい。そこだけに目を向ければ、ハードSFの一種にカテゴライズされる作品である。とても家族向け映画とは思えない。かなり思い切ったオリジナルストーリーだろう。
そんなシリアスな状況下のサバイバル・アクションにおいて、アンガス・マクレーンはギャグとユーモアをできうる限り、取り入れようとしている。バズが同僚からプレゼントされる猫型ロボット、バズの作戦を補佐するダメ隊員たちなどはコメディーリリーフとしてくどいくらいに機能しており、SFに無知無関心の観客でも気楽に楽しめるはず。とりわけ、クライマックスの信じがたい「現象」では、その理由に頭を悩ませることなく、目前のバトル・アクションに乗っていくことができるのではないか。
CG映像も素晴らしい。繰り返すが、今回はおもちゃが主人公ではない。「実写映画」という設定の物語をCGで表現しているのである。したがって、アニメーションであっても、どこか人間的な動きの表現、その繊細さ、本物感が随所ににじんだ。とにかく、バズはスペース・レンジャーとしてりりしく、カッコイイ。こんな活躍をするヒーローを見てしまったら、彼のアクション・フィギュアが欲しくなるというもの。そんなワクワク感こそ、アンディが味わった気分。この映画を見る観客は皆、アンディになる。
最終的に温もり豊かな友情劇へと着地する作品は、同時に登場人物たちの大胆な決断も描く。それは『トイ・ストーリー4』(2019)でウッディが示したそれどころではなく、楳図かずおの傑作漫画『漂流教室』(1972-1974)のラストで少年少女たちが見せた勇気に近い。その一点においても、この作品はかなり高度な人間ドラマになっており、観客によっては帰宅後、子どもたちと一緒にアインシュタインの相対性理論や、宇宙探検をめぐる未知なる明日の話題で盛り上がることができるかもしれない。感動的である。
蛇足ながら、映画『バズ・ライトイヤー』(2022)は、ノン・ピクサー作品『スペース・レンジャー バズ・ライトイヤー 帝王ザーグを倒せ!』(2000/タッド・ストーンズ監督)とは無関係。その後に製作された続編的テレビシリーズ『スペース・レンジャー バズ・ライトイヤー』(2000-2001)とも別次元のスピンオフ作品と考えた方がいい。いずれにしても、バズは今日も宇宙のどこかで戦っている。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。