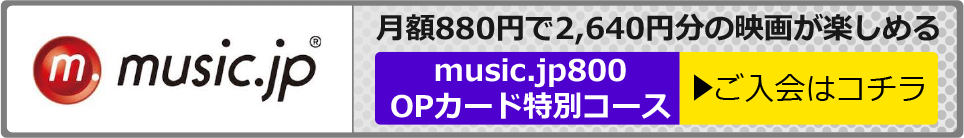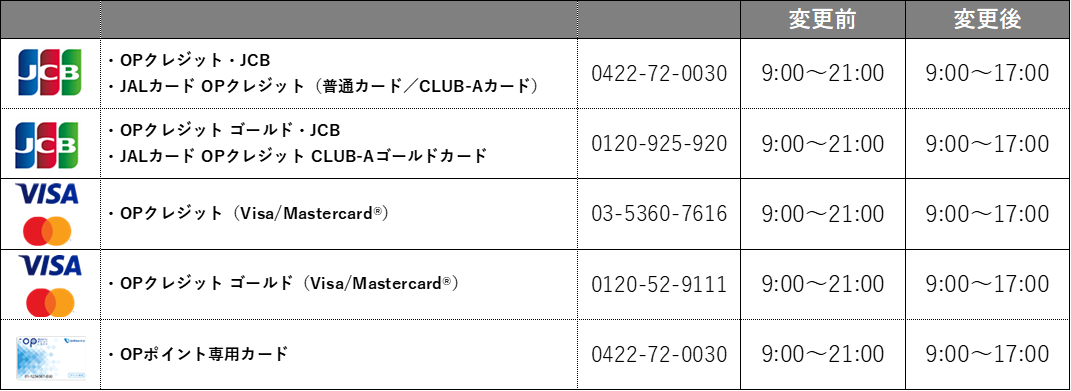特集・コラム
映画のとびら
2022年9月15日
ザ・ディープ・ハウス|映画のとびら #203

 © 2020 -RADAR FILMS –LOGICAL PICTURES –APOLLO FILMS –5656 FILMS. All Rights Reserved.
© 2020 -RADAR FILMS –LOGICAL PICTURES –APOLLO FILMS –5656 FILMS. All Rights Reserved.『屋敷女』(2007)、『レザーフェイス/悪魔のいけにえ』(2017)で知られるフランス人監督タッグ、ジュリアン・モーリー&アレクサンドル・バスティロによる水中ホラー。動画の再生数アップをねらって湖底に水没した屋敷を撮影しようとしたYouTuberカップル、その恐怖体験を描く。主人公男女にミック・ジャガーの息子ジェームズ・ジャガーと、モデルとしても活躍しているカミーユ・ロウ。製作総指揮は『トランスポーター』(2002)、『タイタンの戦い』(2010)の監督ルイ・レテリエ。
ウクライナをはじめ、世界各地のいわくありげな廃墟を渡り歩いているYouTuberカップルのベン(ジェームズ・ジャガー)とティナ(カミーユ・ロウ)が、さらなる再生数をもくろんで選んだ新たなターゲット、それはフランス南西部のフレー湖に沈んでいるという秘密の屋敷。たまたまその所在を知っているという初老の男ピエール(エリック・サリヴァン)と出会ったふたりは、彼の案内で森の奥深くにある湖へと到着。潜水の準備をしながら、ベンがティナに言う。「動画が100万回再生されたらラスベガスで挙式しよう」。そんなふたりにピエールは「プロポーズにぴったりの場所だ。(屋敷へは)階段に沿って下へ行けばいい」と声を投げかける。湖の中に階段? 疑問に思いながらドローンを携えて湖に潜ったふたりは、途中でまず妙に新しい自動車を、その数分後、崖伝いに階段を発見する。さらに進むと、立ち入り禁止の札やマリア像が結びつけられた門を、続いて「モンティニャック家」と名のついた邸宅を見つけるのだった。
スカした若者がよせばいいのに危険な場所へ不用意に足を踏み入れてひどい目に遭う――。そんなホラー映画の伝統を踏襲したかのような展開は、やはり『13日の金曜日』(1980)の系譜にあるといっていい。取材撮影から一転、得体の知れない怪奇現象に巻き込まれるという設定などは、主観映像の多用も含め、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999)とやっていることが変わらない。廃墟を回るYouTuberというキャラクター設定も最近では『牛首村』(2022)が実行済み。その意味では一見、手垢がついたおなじみ企画といえそうだが、だからこそ安心して恐怖を楽しめるという見方もできるだろう。
新味をあげるなら、やはり水中での恐怖体験、これに尽きる。酸素ボンベを背負っての身重の体裁では動きも鈍く、逃げ場も少ない。ボンベの酸素容量が60分という設定も気がきいていて、全くのリアルタイムというわけではないが、ほぼ同じ尺で同時進行的な緊迫感がにじむ。つまり、『真昼の決闘』(1952)のようなカウントダウン式映画でもあり、モタモタといつまでも森の中を這いずり回るような駄目ホラーの愚も冒していない。十分、筋肉質の仕上がりであり、見ていて思わず息が詰まる。溺れそうになる。
ドラマ的な韻もきちんと踏んでいる。導入部分、ヒロインがバスタブの湯につかり、どこまで息が止められるかを試している。がんばって3分が限度。このフリがどうドラマに生かされるのかも見どころのひとつ。やはり、逃げ場のない水中という状況が生きている。監督たちのセンス、悪くない。
リアルタイム的な描写に加え、実際に水中にセットを組んでの撮影も実感が伝わって効果的。カップルが邸宅に閉じ込められて以降は、もう純粋なオバケ屋敷映画と考えて間違いない。ロバート・ワイズ監督の古典ホラー『たたり』(1963)を連想するファンもいるだろうし、スチュアート・ローゼンバーグ監督の実話もの『悪魔が棲む家』(1979)を懐かしむ向きもあるだろう。トビー・フーパー監督作『ファンハウス 惨劇の館』(1981)のような見世物小屋的狂騒を感じる者も出てきそうだ。
スラッシャー風の殺人描写はないが、超常現象をめぐるショック演出は満載。動くはずのないものが動く。いないはずの何かがそこにいる。屋敷の正体がわかったときは後の祭り。すべては自業自得。飛んで火に入る夏の虫。心臓の弱い人は薄目で恐る恐るカップルの行方を追っていただきたい。
公式サイトはこちら
1966年生まれ。文筆家。映画、テレビ、舞台を中心に取材・執筆・編集活動、および音楽公演の企画、講演活動も行う。現在『キネマ旬報』にて映画音楽コラム『映画音楽を聴かない日なんてない』を隔号連載中。